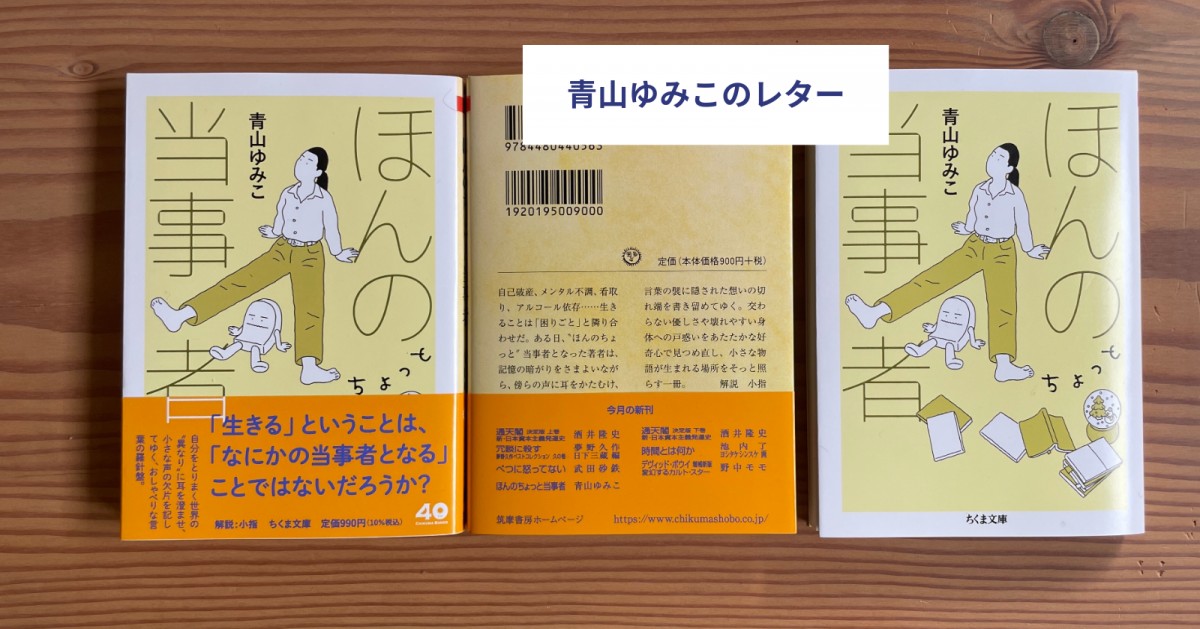指先のじんじんにご用心
皆さん、こんにちは。師走のスタートのピストルがぱああんと鳴り響き、いや、でも、序盤はほどほどに助走で〜と思っていたところ、いきなり「え、障害物競走だったの!?」という12月第1週を過ぎた青山です。
コースを脱線してるのか、そもそも不安定なコースというのが安定の予想どおりなのか、もうわからん。
先週の火曜日、大学の授業を終えて、六甲の中腹から街におりて、自転車で近所のスーパーまで戻ってきてから、ふと思いついて、そのすぐ近くにある整形外科クリニックに寄ってみました。
ひと月ほど前から、いや、どうだろう。そろそろ2カ月ほどになるのかなあ。右手の中指の先っちょが、じんじんと腫れたり、腫れがひいたりを繰り返しながら、でもいつも小さく痛んでいる。
めちゃくちゃたいしたことない自覚症状なので、何十日もほっていたけれど、今日は痛みが10段階でいうと6か7。ちょこっと消毒薬か塗り薬でももらって帰るか。
めちゃくちゃ気軽な気分で、街の小さなクリニックを受診したというわけでした。
ほどなく診察室に通されると、何度かお世話になっている逸見政孝似の四角いフレームグラスでジェントルな雰囲気の先生。舞踏会に連れ出すようにそっと手を取って、指先を眺めながら、わたしの話をやさしくふんふんと聞いた。
「念のためレントゲンを撮ってみましょうか」
そうだった。整形外科って「とりあえずレントゲン」なんだったと久しぶりに思い出した。
さくっとレントゲンを終えて、再び診察室へ。
「骨にはとくに問題ないですね〜」
「やっぱりそうですよね。こんなたいしたことない状態で病院に行くのどうかな、って迷ってたんです。ほっといたら治りますよね」
苦笑しながら、たいしたことなさすぎて正直恥ずかしかった。レントゲン代、損したとセコい考えまで浮かんだ。
だけれど、ニュース報道のキャスターみたいに、先生の眼鏡の奥の目が冷静だ。
「これね。骨には問題ないけど、なかにばい菌が入って化膿してるみたいやねん。ちょっと爪を取って見てみたほうが良さそうやと思う。いいかなあ?」
「あ、そうなんですか。じゃあ、お願いします」
答える前から、看護師さんがわたしの横に処置台みたいなものを設置して、ワゴンに処置道具みたいなものを乗せて運んできた。
え!?
銀色のワゴンの上に載っているのは、まあまあデカ目の、澁澤龍彦みのある工具のペンチばさみなやつ。
「あ、あの、、、痛いですか?」
「うーん、ちょっと痛いかもしれんねえ。爪を少し取るから」
ツメヲスコシトルという音に急に冷や汗が出て、あわあわしている患者を目にした看護師さんが、忍者みたいな素早い動きでわたしの背後に回り込み、まるで一年ぶりに会う彼女を驚かせないように後ろから抱きしめるみたいな感じに、やわらかく、しかし強固に上半身をロックした。
な、なに、このシチュエーション。わたしは暴れるという想定? そこまで痛いというわけなのか?
「大丈夫ですよ」わたしの両腕を背後からロックしながらさすさすとさする看護師さん。すごくやさしいなで方で、一層と恐怖が増す。やさしさが怖いよ。
わたしは刃物も尖ったものも視覚的に苦手で、普段の血液検査でも注射針も絶対に見ない。大好きな韓国ドラマでも、サスペンスものはほとんどみない。切るとか刺すとかがめちゃくちゃ苦手なんだ。
恐怖のあまり、処置台に乗った自分の腕からできるだけ顔を遠ざけて、のけぞるような姿勢を取るわたし。背後から押し返すような抱き締めナース。身体と身体の肉弾戦、静かなる攻防戦。大人なんだから我慢しなきゃ。いよいよ処置が始まったみたいだ。
「ちょっと痛いかもしれんよ」
ばちん。
ヒィィィィ!!!
「ああ、膿んでるねえ。もうちょい爪とるね」
ばちん。
ヒィィィィィィィィ
声も出なかった。息が音になったみたいな。死ぬかおもた。
現実からあまりに目を背けたせいで、これ以上詳しく書けない。なにが起きていたのか見ていないからわからない。とにかく爪が少し減って、排膿されて、消毒薬が塗られて、絆創膏を貼られていた。
そんなわけで、先生にしたらきっとうんざりするほどやってきたであろう「ひょう疽」の治療が行われ、じんじんと続いていた痛みは見事に消え去って、処置による際の軽い切り傷くらいの感触だけを残し、翌日経過を診てもらって、今はもうばっちりオッケー。
原因はおそらく、切り残しの爪が皮膚の奥に入りこんで、そこが膿んでいたんじゃないかってことでした。もう原因までたいしたことなさすぎる。
でも、ひょう疽は放っておくとさらに化膿して、最悪の場合は骨まで腐らせてしまう可能性のある、それなりに怖いものなんだそう。