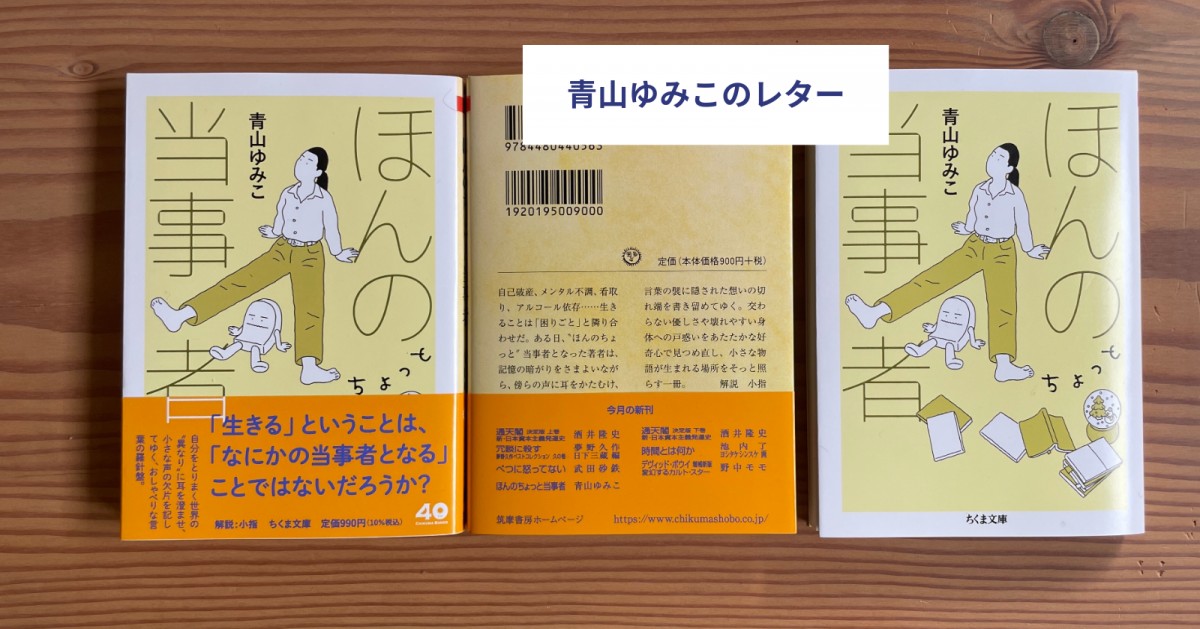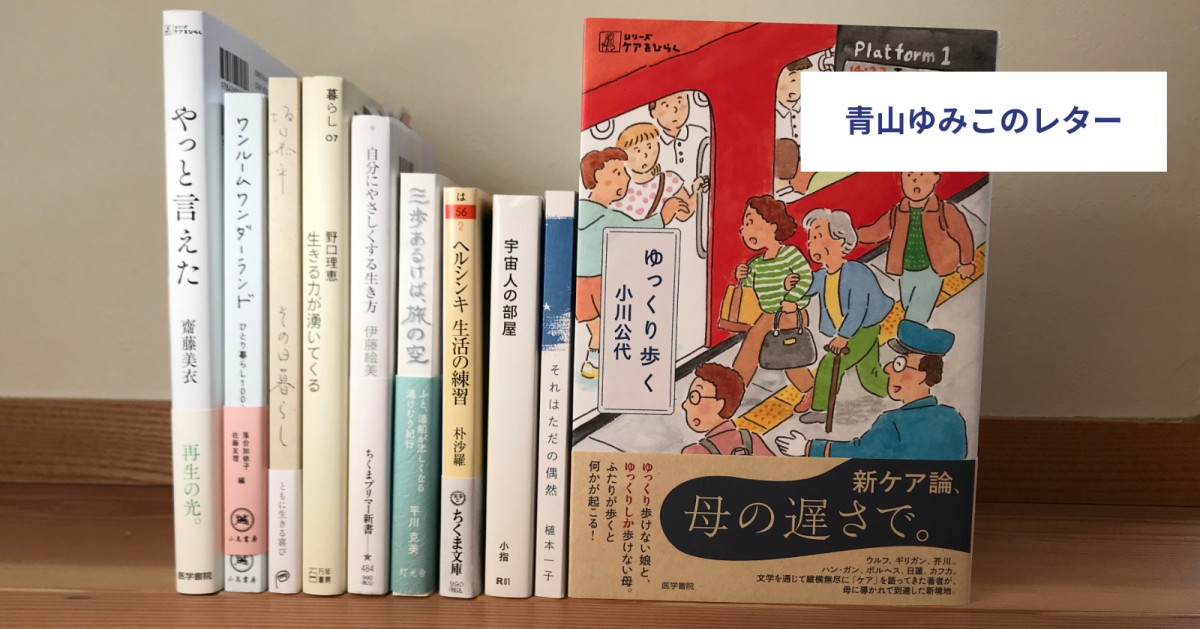年をとるってやっぱりわからない日記2.1-2.10
2月1日(土)
朝は、横道誠『「心のない人」は、どうやって人の心を理解しているか──自閉スペクトラム症者の生活史』(亜紀書房)から「はじめに」「序章」を読む。マコトAとマコトBによるやり取りという形式で、本文中にも二人のやり取りが入るのも面白い構成。
横道さんは書かれる内容も独創的だけど、こうしたカタチのユニークさも味だといつも思う。ご本人の「生きづらさ」みたいなものが研究や創作の元にあるのかもしれないが、ご著書からは伸びやかな自由も同時に感じる。
ちょっと力のいるメールやり取り。「断る」というのが苦手な人生を送っていたのだが、ここ数年、断る筋トレみたいなことも普段から意識しているせいか、以前より苦手ではなくなってきた。
「なーんかひっかかる」みたいなとき、できるだけ感情を抜いて事実だけを再点検してみると、やっぱりなにかしら小さな問題があったりして、そのほとんどが「理にかなっていない」ことだったりするように思う。
モヤっとひっかかったときは「感情」のような気がするけど、案外「理屈」の問題なんよなあ。微妙に筋が通っていないとか。なので、ドライに理屈で物事を整理してみると、自分に筋が通せるから、なにかを断る自分にも罪悪感が残らない。
「自分に対する小さな罪悪感」って、心のキャッシュのようにいつの間にか貯まって重くなるので、普段からできるだけつくらないように心がけている。というトレーニングの進行形です。できればあっさり生きていきたい。年をどんどん重ねる今後はとくに心を身軽にしたい(願望)。
午後はジム。系列店からトレーナーさんが来ていて、レッスン内容はいつもと同じなのになんだか新鮮だった。自分がとことん飽き性なので「新鮮さ」というのはほんと貴重。継続には「ちょっとした変化」が必要で、外からくる「変化」もあるし、例えば今日は音楽を楽しもうとか、「自分がつくる変化」もあるのかも。なんてことにようやく気づいてきたジムに通い始めて2年の候。
夫が今日も忙しそうなので、晩ごはん用に「濃厚鶏白湯」の鍋用スープ、骨付きの鶏もも肉、生つくねのたねを買い、メッセンジャーで写真を送る(晩ごはんはこれやで的に)。
母の命日だけど特になにもせず、お花を飾っている理由をそれとなく告げると、「お母ちゃん、かわいそうやったなあ」と夫が呟く。母の最後の入院時、夫が毎晩ごはんを作ってくれて、気力だけで生きてて食欲なんて枯渇していたようなわたしが病院から帰宅すると、牛すね肉を煮込んだシチューとかやたらご馳走が毎晩並んだ。味は覚えてないけど、そうやって自分のために誰かが料理をしてくれたという記憶は消えないものだ。
2月2日(日)
朝は、横道誠『「心のない人」は〜』の続き。
少し前にライター仲間の姫野桂さんから高級昆布をお裾分けいただいたことがあり、ちょっとした御礼になにか……と迷っていたのだが、ふと思いついて神戸の地ソース「ばらソース」の焼きそば用ソースなどをレターパックで送る。厚みが出てポストに投函できないので、少し離れたハーバーランドそばの中央郵便局まで自転車で往復40分ほど。
どんなに寒くても、メンタルの調子が落ちて動けなくなった頃から、自転車でびゅんびゅん走るのは嫌じゃないことのひとつ。「今いるここから離れたい」という気持ちの自由と、「自分がまだ動ける」という身体的な自由。心身のどちらにも自由を感じることが、わたしにとって自転車を漕ぐことなんだと思う。
晩ごはんは夫が骨付きのもも肉をスパイスで煮込んだチキンカレー。ナンで食べるタイプのしゃばしゃばのやつ。そういえば二日連続鶏やな、と食べ始めて二人で気づく。
東京でAddiction Report1周年イベントが開催されて、SNSで熱い投稿をいくつも目にして泣きそう。ツイログみたらめっちゃRPしてた。
2月3日(月)
思い出したことがあり、東畑開人さんの『聞く技術、聞いてもらう技術』(ちくま新書)を読み返す。「奥義オウム返し」とか「わからない」を使うとか、すごく実用的なポイント(実例)が細かくわかりやすく言語化されていて、最初に読んだときに付箋をつけたら、ほほ全ページについてしまって意味ないじゃんとなった本。読み返しながら外して、また横に移動させてつけてしまうという。
コロナ禍で始まった東畑さんのオンライン臨床心理学講座を3年ほど受講していたが、「惜しげもなく」という言葉でも足りないくらい、いつもたっぷり聞かせてもらった。わたしの周りにも東畑さんのファンが多い。きゃっきゃとなってしまうわりにミーハーな「ファン」。わたしもそのひとり。
「コーピング」と「韓国ドラマでセルフケア」についてのレターを配信。読んですぐに感想を書いてくださった方が何人かいて、読まれるという体感はやっぱりなにより嬉しく胸がぽぽっとあたたかくなる。わたしには書くこともコーピングのひとつ。いただいたコメントを読むこともコーピング。お勧めドラマを教えてくださった人も多くてメモしまくった。皆さん、ありがとうございます。
新しく担当する科目のシラバスをようやく入力完了。内田樹先生の『街場のメディア論』(光文社新書)に軸足を置きつつ、いろんなメディアの現場の「声」を取材した素材を使うという授業計画。つまりわたしがインタビューして、それを授業で使うという流れ。アイデアは悪くないと思うけど、準備がたぶん相当大変……あの人この人にお願いしていく予定(どうぞよろしくお願いいたします)。
※ご登録(無料)いただくとメールボックスにレターをお届けします。わたしの「書く」励みにもなりますので登録いただけますと幸いです。
2月4日(火)
久しぶりに朝寝して8時頃起床。朝ごはん食べて洗濯したら本を読む時間なんてなかった。育児されてる方はきっと毎日が忙しないことだろう。朝にのんびりできるのはわたしがフリーランスで、大人のふたり暮らしだからだと思う。
ばたばたと成績つけのためにレポートの採点を開始。20名弱、15回分(って計算するとさんびゃく? なぜ読んだときにしておかなかったのか……)の文章をひとつずつ読み返して点数をつけはじめる。
誰かが書いたものを数値化するって、ものすごく難しい。授業テーマは「伝わる言葉とはなにか」なので、正解がないから、言葉はもちろんだけど、言葉で書かれていないものも含めて届いてきた強度を評価するようにしている。書かれたものには、書かれていないものも含まれている。
お昼前のレッスンで、キャンセル待ち登録していたものが、繰り上げ受講できることになり、用意してジム。
千葉にある「ときわ書房志津ステーションビル店」主催の志津ノーベル賞2025 エッセイ部門に『元気じゃないけど、悪くない』(ミシマ社)が選ばれたことをSNSで知る。まぢで!? と涙。ビジネス部門では牟田都子『校正・校閲11の現場』が選出されていたり、好きな本、気になっている本がたくさん受賞されていて、いちいちRPしてしまう。志津ノーベル賞の受賞作一覧が並ぶフェアは、3月末まで開催。行けたらいいなあと、Googleマップで場所と、神戸からの経路を確認してみたりするだけでどきどき。想像するだけで十分に胸って躍る。
夜は夫が宇治川商店街の精肉店でええのがあったと買ってきたホルモンでもつ鍋。つゆはくばらの博多もつ鍋のあごだし醤油味。ニラどっさり。ものすごく温まる。
それで終わればよかったけど、ちょっとややこしい電話が夫にあって、ものすごくややこしい状況になる。ややこしすぎて書けないのだが、自分たちのどちらが悪いということでもなく、ただ、お互いに自分の人生を生きていて、それぞれなにかあるってことを改めて実感するような出来事。
しょうがないと頭で理解していても、巻き込まれるのは理不尽な気持ちになるのは避けられない。寝るお薬を早めに飲んで、強引に就寝。
2月5日(水)
朝は、『韓国ドラマを深く面白くする22人の脚本家たち』 (ハンギョレ21・シネ21著/岡崎暢子訳/クオン)。「梨泰院クラス」から「私の解放日誌」までというサブタイトルどおり、たくさんのドラマが21人の脚本家インタビューから紐解かれる一冊。次に見るドラマ探しも兼ねてぱらぱら読む。つい、自分が見たことあるドラマを探して読んでしまうので、それでは新しい作品を探せないじゃないか。と思いつつ、そういうのってありますよね……。
お昼前に、映画監督の神保慶政さんが神戸に来られるということで、元町商店街のにしむら珈琲店で待ち合わせてお茶。お会いするのは初めての神保さんには、ダ・ヴィンチWebで『元気じゃないけど、悪くない』や『ほんのちょっと当事者』の書評レビューを書いていただいていたので、直接御礼が言えて嬉しかった。
話はとりとめなくとんで、流れで商店街をそのままつつつと一緒に西に向かって歩き、商店街3丁目の元町映画館をのぞく。映写技師の和田たすくさんがおられて、藤野知明監督作『どうすればよかったか?』のお話が少しできて、「連日すごく入っている」とお聞きした。帰りにイスズベーカリーに寄る。
午後はひたすら、成績つけのためのレポート採点の続き。もう時間がないよ(自分に軽く追い込みをかける)。
少し前に打ち合わせをして文字起こしが上がってきて、メールのやり取り。よい感触。良いものが書けそう(という感覚のときはもう書けた気になる。書けてないけど)。
2月6日(木)
朝読み本は、瀬尾まいこ『そんなときは書店にどうぞ』から、ついに『夜明けのすべて』(水鈴社)に辿り着いた。
レポート採点が終わったけど、成績つけるのはさらに難しい……。授業のなかで、学生それぞれに「スイッチが入る」タイミングも違うし、扱うテーマへの関心のあるなしや、やっぱり相性ってある。なにより生身の人間だから体調が悪いかと、眠たいとか、その都度変わる。これは教壇に立つ自分も感じる。
例えばもう一回授業があったらどうだったろう。どんな文章を書いたのかな……そんなことも想像させてもらえる学生たちだった。またまたなんだかさみしくなってしまう。センチメンタルすぎや。
大阪池田の「ふるえる書庫」の、コミュニティメンバー募集がCAMPFIREで始まったので早速登録。緑に囲まれた空気のきれいな古江町。古民家を改装した私設図書館で、3万冊の本に囲まれためちゃくちゃ気の通りのいい空間。縁側もすんごく気持ちいい。
2月7日(金)
午前中、歯医者。ついにかぶせをかぱっ。昨年11月からかかっていた奥歯の精密根管治療、ようやく仮止め。初めての自費診療ゾーン、いろんな意味で大変だったので「あくまで仮」とはいえそれなりの達成感。芸能人じゃなくても歯は大変だよ。年を取るとますます感じている、歯は命。いろんなものを思い切りがしがし噛みたい。うぅ。
歯がおさまったうきうき気分でジュンク堂書店三宮店に寄り、村山由佳『PRIZE
ープライズ』(文藝春秋)。帰宅して、トイレさえ我慢してページを捲って、久しぶりに日をまたがず一気読みした(いつぶりだろう)。めちゃくちゃ胃が痛いし、めちゃくちゃ面白かった。スーパー怖い話でもあるのに、最後の最後の最後にどんでんがえってめちゃくちゃ胸が熱い。すごくないですか。ラストの一行がまぢすごい。
わたしはひたすら「編集者として」読んで、2箇所で笑い、2箇所で涙出た。この作品の担当編集さんにインタビューしたいくらいだ。書きたいこと山盛りだけどネタバレになりそうで書けない(ぐるじい!!!)
2月8日(土)
瀬尾まいこ『夜明けのすべて』(水鈴社)読了。
主人公はPMSとパニック障害の当事者。不安障害でパニック発作を頻発したわたしは、思いがけず自分のあれこれを再確認するように読めた作品だった。思えば、ずいぶん調子悪くなく過ごせるようになってる。同時に、浮遊性めまいがあるので夜は外出しないし、そんなふうに自発的に控えていることもある。自分で自分を制御するみたいなこと。そのことが引っかかってもいたんだな、でもそれでいいんだな、と大きく肯定できた気がしたことも嬉しかった。
たった今、自分で「やりたいことを我慢してる」という気持ちはほとんどない。「諦める」という感覚も実はあまりない。むしろ、「できること」を、やりたいようにやっている。だから「これで悪くない」って思ってるんだなあ。
10日締切の成績点け、そろそろ焦ってきた。全集中でこりこりこりこり。 脳みそばかり使うとバランスが悪いので、身体を動かすべくジムも予約。脳と身体と両輪で回すと、自分の動きが潤滑になる。
ジム帰りに1003に寄ると、お目当ての本はまだ入荷待ちで、大西寿男さんの『みんなの校正教室』は売り切れ再入荷待ち。いいの、いいの。本との出会いのタイミングってあるから、むしろこういうのも本屋さんの楽しみだったりもするのよ。待つぜ。

1003では元町映画館とコラボの「鑑読往来」フェアが開催中で、ゲンナイ本もひょこっとフェア棚に混ぜてもらっていて、じーん。本に出てくる坂上香監督『プリズン・サークル』は、神戸では元町映画館で最初に上映された。三好大輔・川内有緒共同監督作『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』もそうだ。少し前に二村真弘監督『マミー』も元町映画館で見た。いいミニシアターはいい本屋さんと同じで街の大事な存在。斎藤真理子さんの『増補版 韓国文学の中心にあるもの』(イースト・プレス)をようやく入手。
2月9日(日)
内田樹先生の『図書館には人がいないほうがいい』(朴東燮編訳/アルテスパブリッシング)を再読。知性とは、脳内キャッシュを落としてくれる浄化作用があることを相変わらず実感し続ける内田先生節が最高に心地良い。書物は私有物ではなく公共財である。内田先生は例え話が痒いところ掻かれたみたいに気持ちよくうまいんだなあ(わたしが言うのも今さらですけれど)。訳者であり編者である朴東燮先生のご寄稿もすごい読み応え(何かが憑依しているよう)。
成績点け、入力完了! ゴールのテープを切った瞬間のやりきった感。ひとりで小さく「うぉぉ」と叫ぶ。飲んでいた頃なら今夜は絶対に泡とか開けてたよなあ。でも、絶対に飲まなきゃ気がすまないというわけでもない。最近は「飲みたい」「飲まない」について、意識的に小さく自分に質問するようにしていて、今日も聞いてみたところ、そこまで飲みたくないみたいだった。
理由を考えてみると、少しずつ取りかかったのでそこまで負荷がかからなかったこと。SNSで「大変だ」と弱音を吐いてみたり、ジムで汗をかいて脳みそからっぽにしたり、「精神的な負担」を小さくあちこちで散らしていたからじゃないかな(仮説)。
仮説を立てて検証することを繰り返すなかで、自分によさそうなものだけ「本採用」して、自分だけの取扱説明書(取説)をつくっているところ、みたいな最近。
午後、オンラインで打ち合わせ。その後、来月にお招きいただいた講演のスライドを作る。パワポじゃなくて、初めてCANVAで作ってみた。CANVAはデザイン力が本当にすごい。でも画面を見過ぎて、目が潰れそう……。歯も大事だけど、目も大事。間違いなく老化は進んでいる。夜はもうパソコンの字とか見たくない(目がかっさかさで)。
2月10日(月)
お昼に見る韓国ドラマがまだ本決まりしないので、なんとなくチョン・ジア『父の革命日誌』(橋本智保訳/河出書房新社)を手に取る。読み始めてすぐに、「ああ、これはしっかりどっぷり読みたいやつだ」とまた気づく(これで何度目だろう)。時を待つ本ってある。
歯を磨いていたら仮止めしていたかぶせものが洗面台の流しに、からりん、と落ちる。もう少しで排水口に流れてしまうところだった。ちょっとしたブランドもののバッグくらいの値段のものが……ひぃーー!!と心臓が縮み上がる(まぢで半泣きした)。クリニックの受付と同時に電話して、お昼前に予約が取れた。ただ先生がお休みのため、仮止めできないので、再び仮埋め。3歩進んで2歩下がるみたいな。うぅぅ。
3月「ゲンナイ会」の受付告知を出す。気づけばもう11回目になる。お昼を食べたあと講演のスライドを完成。
極度の乾燥肌で、かっさかさの足のすねを掻きむしって血が出たので、午後診開始に合わせてかかりつけの皮フ科で塗り薬をもらいにいく。医療保険制度に助けられている身には、ここ数日SNSで目にするようになった高額療養費制度の自己負担分が引き上げ案について思うこと多々。わたし自身はまだ利用したことがないが、周りで助けられている人が多い。もちろん反対の意思表示をしていく。社会福祉制度は関係ないようですべて自分事。いつでも自分の立場って変わるんだから。
(つづく)
メンバー登録いただいてメールレターで読んでくれている皆さん、本当にありがとうございます。次回は4/7(月)に配信予定です。
◉ ◉
【お知らせ】
●4月「ゲンナイ会」のこと
わたしが暮らしている神戸で毎月開催している「ゲンナイ会」という、読書会のような、自助グループのような会の受付のお知らせです。のんびりした会なので、ご興味ある方はどうぞ(4月はあと1名受付可能かなという感じです)。
●「話を聞きます」受付のこと
2年ほど前から、一対一でお話を聞く、インタビューセッションのような場を開いています(大学の授業がない時期だけなので8月末までの期間限定です)。わたしは本当に話を聞くだけの、ちょっと不思議な場です。ご興味ある方はこちらをご覧ください。
●サポートメンバー登録のお願い●
いつも無料版のニュースレターをお読みいただきありがとうございます。
わたし自身が心身の不調でしんどいときも、本や本屋さん、図書館をはじめとした「本のある場所。また、こうして無料で読めるオンライン記事に助けてもらった体験があります。そのため、誰にでもお読みいただける記事をできるだけ継続してお届けしたいと思っています。
とはいえ、お仕事しつつ週に1度のレターを書くのは正直、楽ではありません。始めてみたら、わりと大変だと気づいた次第です……(ひゃああ)。
なので、できれば有料サポートメンバーとして、執筆支援いただけたら、とってもとってもありがたいです。このレターは有料サポートメンバーの方のおかげでお届けできています。書くほどに、そのことをしみじみ感じています。 また、わたしの「書く」大きな励みになります(本当に)。
サポート額は自分の好きな額を選べます。月額は読者さんが自由に設定することもできます。いつでも変更・解約ができます。どうぞよろしくお願いいたします。
心身のリハビリについて書いた著書はこちら。ケアの実践書のような本です。
『元気じゃないけど、悪くない』(ミシマ社)

すでに登録済みの方は こちら