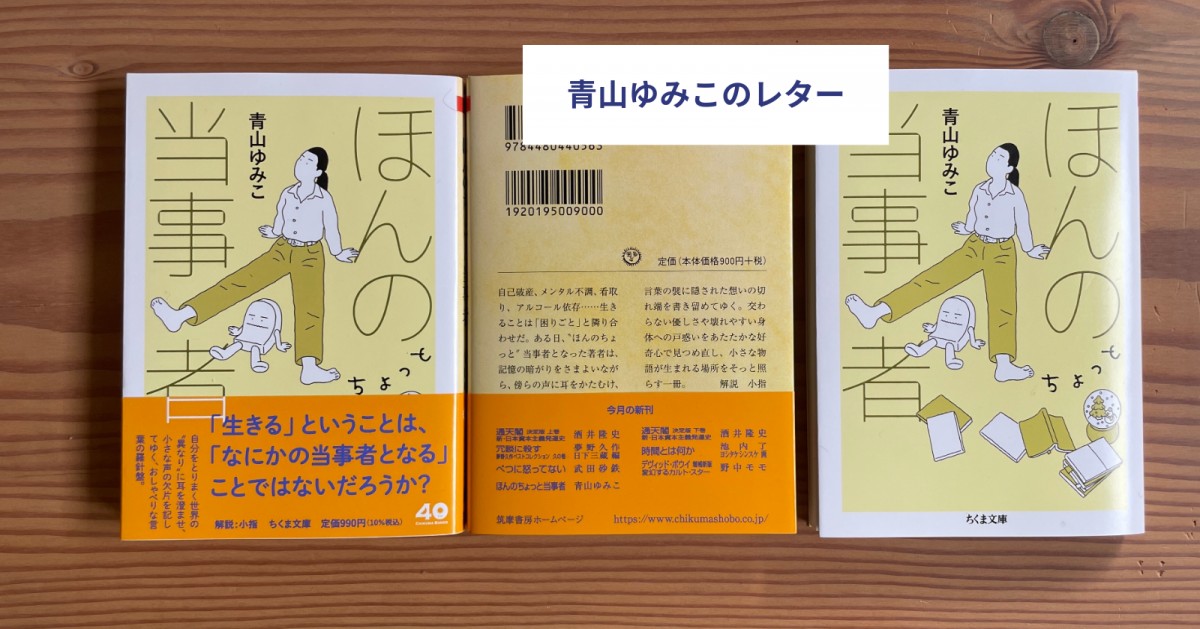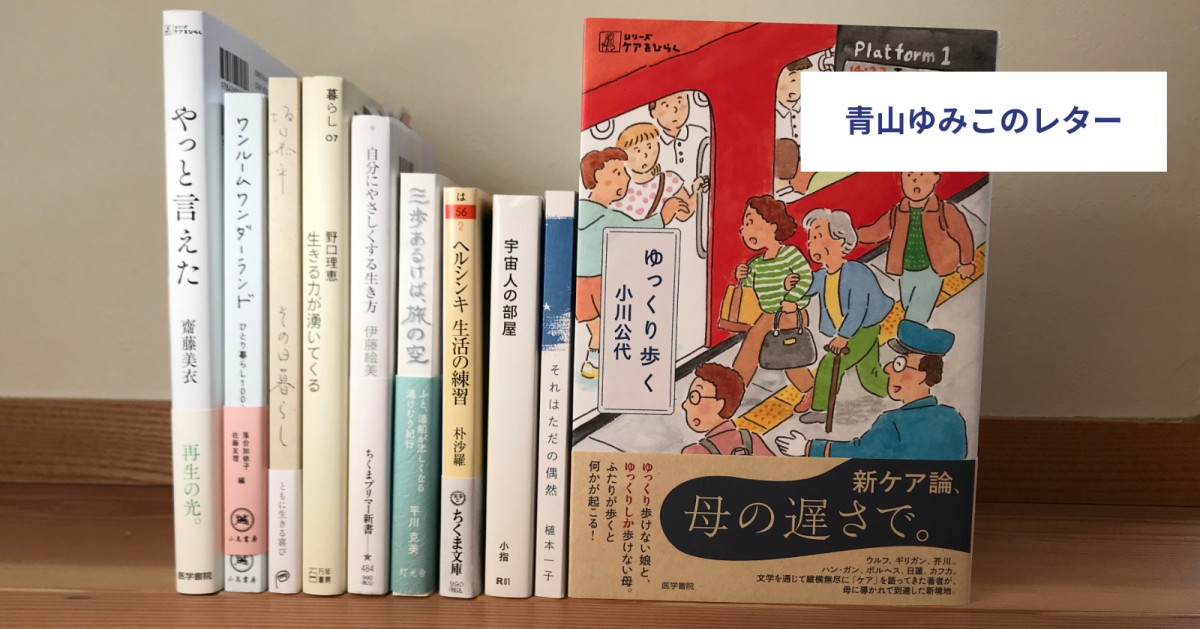「読む」わたしの長い言い訳。「校正」こそ、書く力
こんにちは。
前回の、つまりわたしの「はじめてのレター」をお読みいただき、ありがとうございました。あのレターは書いてすぐにでも送りたい!くらいの気持ちでしたが、そうしなくてよかった。
今日はそんな「校正」のお話です。
●
2025年の仕事始めとなった人が多いであろう6日、月曜日。
久しぶりに職場に行くとどこか新鮮な気持ちもするんだけど、やっぱりなんだか気疲れする。「お休み明け」ってそんな日だったりする。
勤め人時代、月曜日はいつも気がどこか重かった。特に嫌なことがあるわけでもなく、いい感じに気がぴんぴん張ってるときもあったけど、それでもなんだろう。
「これから火曜日、水曜日、木曜日、金曜日……」と次の休みまでの日数を指で折って数えると、「こんなに……」と見てはいけないものを見たような。
そんな意識から目を逸らすように、帰りにおいしい甘いものを買って帰ったり、駅前で軽く一杯飲んでみたり、いろんなやり方があると思う。いろんなやり方があるといいな、と思う。
このレターも月曜夜の憂鬱をちょっと和らげるものになればいいなあ。
なんてことから、このレターの配信は月曜17時に決めたのでした。
もちろん平日休みの人もおられるでしょうし、勤務時間帯もいろいろだと思います。わたしもフリーランスだから暦通りじゃないんだけど、でも、「月曜夕方の気分」ってありますよね。メールレターはあなたにとって良きタイミングで読んでもらえたら嬉しいです。
●
話は新年5日の日曜に戻る(お正月なんてもう去年のことのように思える……)。
前傾45度の前のめりのわたしは、前日に勢いで書き上げた最初のレターを配信設定画面に流し込んだり、レターの名前を決めたり、プロフィールや概要なども一通り整えてみたりしてみると、もうあとは配信ボタンを押すだけになった。
ほっ。
としている場合ではなく、やるべきことが別で積み上がっていた。
昨年から神戸の阪神間にある大学で非常勤講師としてコマをもっていて、いまは後期の真っ最中。今年最初の授業日が2日後に迫っている。
「読む」と「書く」を主軸としたこの授業では、授業後の課題としてショートストーリー(自分の話)を書いてもらう。
それに対して、次の授業までに、届いた課題を読んで「感じたことを書いて伝える」。ということを毎回毎回繰り返している。
誰かの話を読んだり聞いたりするのが大好きなので楽しんでもやっているが、自分的にはかなり本気を出している。学生からすると、どうなんだろう、うざいかもしれないくらい、真剣に返信を書く(必然的に長くなる)。書かれたものは、誰かがちゃんと読むってことを伝えたくて。伝わりましたって反応が届くこともあり、励まされている。
履修生は20名ほど、やっぱりひとり30分はかかっている。単純計算でも10時間。集中力を切らさないようにかかるので、脳みそがつるつるになってくる。
繰り返し、頼まれてもいないのだが……。自分が人からそんなふうに読まれたことがあるので、わたしもそうするのだと思う。
授業は火曜の午前中。
そんなわけで日曜、終わらなかったら月曜に引き続き、と後期は週末に他の予定を入れないでかかりきりでMacBookAirに向かっている。
手をかけすぎてるとわかっているけれど、「読む」と書かずにはいられない。「読む」ってことは、「書く」を生業にするわたしには、とても大事なことだから。
今回は期末の特別課題だったこともあり、熱の入った文章が届いて、思わずぐっと読んでしまうわたしはいつも以上にスイッチが入って、ひたすらケンシロウのようにキーボードを連打。
乾季のサバンナのようなかっぴかぴのドライアイで、ようやく授業用にまとめたデータを学生との共有画面にアップしたのが月曜の16時を過ぎたあたりだった。
はああああああ。
とひと息ついたところで、気がついた。そうだ、そろそろはじめてのレターの配信時間ではないか。わくわく。
と同時ににわかに不安がこみ上げた。どきどきどきどき。読み返しておいたほうがいいよね。なんせわたしはめちゃくちゃ誤字脱字の多い、誤字脱字クイーンなのだから。
いちばん多いのが「文字の消し忘れ」みたいなものだ。
「文字の消し忘れ」
「文字の毛しわすられ」
なんて具合に、消しゴムの残りかすみたいな「毛」とか「ら」みたいものが残っているパターン。
慌ててプレビュー画面を立ち上げて、頭から読み返し始めたところ、わっさわっわあるわあるわ。誤字脱字もそうだけど、重複する言い回し、語尾。気になり始めたら止まらない。恥ずかしすぎる。
脇の下をぐっちょり濡らしながら、結局16:59までちくちく触り続けていたのです。
というか「59」の数字を見て、ひぃぃ、となり、えいやっとクリックしたあとは、もう怖くて見られない……ぱたんとMacBookAirを閉じた。
そのレターが前回の文面、あれは産地直送以上に「書きたてほやほや」をお届けしただものだったのでした。
※ご登録(無料)いただくと、メールボックスにレターをお届けします。わたしの「書く」励みにもなりますので登録いただけますと幸いです。
わたしは紙媒体の雑誌編集出身で、在籍していた月刊誌編集部では、初校、色校、青焼き(念校)と3度の校正が基本だった。編集部内で回し読みもするけれど、その3つの校正紙は必ず専門職の校正・校閲さんが読んでくれる。
どんなボールもゴール前で止めて、チームを助けてくれるスーパーなキーパーのように心強い存在。それがわたしにとっての校正者Oさんだ。
例えば前回のレターに出てくる言葉でいうと、「元旦」は「元日の朝」を指すので、「元旦の朝」は「胃痛が痛い」のように重複表現となる。そんなこともOさんに教えられた。
Oさんは出版編集に関わる年数が長く、わたしにとってはこの世界の超先輩でもあった。その月刊誌にも創刊当時から関わっていたので、特集、連載などコーナーの趣旨や意図を、まだひよっこ編集者のわたし以上によくわかっている。
誤字に限らず、意図を汲んだうえで「読む」。なので、言葉を正しく整えてくれるだけでなく、編集的な提案をいただくことも少なくなかった。
優れた校正者は、編集的な思考をもっている。オールカバーできる編集的視野がいい媒体を支える。でも、同時に大切なのが役割分担を意識して動くこと。雑誌はチーム仕事なので、それぞれのポジションに責任をもつってことも、彼女が教えてくれた気がする。
編集の面白さや言葉の遊ばせ方、「読む」のゆたかさを教えてくれた一人が間違いなくOさんだったと、彼女の明るい声とともに思い出す。
残念ながら今はもう、その声を聞くことは叶わないのだけれど。
●
フリーランスになってからいろんな媒体に寄稿しているが、それぞれの担当編集者さん&校正さんがいてこそ、「青山ゆみこ」名義で出た文章はなんとか日本語の品質が維持されている。
わたしの文章は、自分一人で書いているわけではない。そんなふうに思うことが多い。
昨秋、『暮しの手帖』(2025年9月25日発売号)に随筆を寄せた際のこと。
最初に原稿依頼を受けたのは4月の上旬だった。提案を受けた締切は7月上旬。
え、執筆期間が3カ月っ(通常の雑誌で、そんなのんびりペース、ありえない……)。
どれだけ余裕をもった進行なのかと、この時点で衝撃を受けていたが、さらに驚いたのは、初校ゲラが出てから再校までまたひと月。その間、編集部の壁に全ページを貼りだして、全員で一枚一枚、一文一文を読むのだとか……。
そんなふうに「紙で出力」して、いわばリアルに可視化して、チームのみんなで共有すると、なぜか新しくアイデアが生まれたりするし、絶対に悪くない。そんなやり方が理想的だとわかっていても、いやあ、これはなかなかできることではない。
大前提として、チームの全員が担当誌面を「締切通りに上げる」からできることでもある。たくさんの人が関わるチームで足並みを揃えるってこと、簡単じゃない。どんな職場でもそうだと思うけれど。
ゲラの校正にも編集部の思慮深い姿勢がにじむようだった。
そっとやさしい声で告げられるように添えられた、読みにくくない程度の細さの校正の青い文字。あくまで控えめで、「ほんのご提案なのですが」と圧がない。内容はこちらにはありがたい提案ばかりだ。
文字ひとつにその人が表れるって、これだなあ。
最初の原稿依頼メールから、お盆の最中の校正やり取りまで、落ち着いて併走してくれたIさんのお人柄にも癒されるようだった。

話が飛んでしまった。
このレターをプレビューでちくちく校正しつつ、相変わらず自分が「誤字脱字クイーン」であると突きつけられ、普段いかに人に助けてもらっているか……と考えさせられていたわたしです。
でも、こうしてウェブ公開するものだと、アップしてからも修正することが実はできちゃいますよね。ただし、登録いただいた読者の皆さんに届けるレターは、一度送信したらもう書き直せない。
手書きの手紙だってそうだ。宛名を間違えたことに後から気づいて汗が噴き出したことが何度もある(後日たまたま判明したり……)。だからといって受け取る人は目くじら立てずに、そっと脳内変換してくれたりする。そういうのはメッセージを「発信した人」と「受け取る人」のあいだに悪くない関係性があるからなんじゃないかな。
実は、初回のレターにもはっきり誤字がありました。気づいたのが配信翌日の火曜日の夜。ウェブ上ではこっそり触っています。
「生原稿」はだから危険。わたしのようなザルの目では誤字を落としまくってしまう。
担当編集者のいない、校正さんにも助けてもらえないこのレターは、パソコンで打った文字ではあるけれど、手書きの手紙のように大目に見てもらえたら嬉しいです。
そんな言い訳がまた今回もひたすら長くなってたというわけでした。とほほ。
そういえば、昨年秋のこと。
神戸の本屋「1003」さんにて武田砂鉄さんとトークをしたときに、お互いに書いたものは必ず「紙に出力する」という話が出た。
「書いた」わたしと、「読む」わたしは別人で、わたしは「読む」自分の方を信用している。
「書く青山さん」は案外素直で、「読む青山さん」からの指摘を素直に受け取るので、ふてくされずに推敲し、書き直す。
この「書く」人格と「読む」人格は、「書かれたもの」が紙に印字された瞬間に、わたしの場合はすっと個別に立ち上がる。書いている間には「読む」人格が出てこない。
なんて話をしたところ、砂鉄さんも原稿は必ず紙に刷りだすとおっしゃっていた。
例えばパソコンが手元になくて、スマホのメモ機能で書いたテキストなら、スクショして、画像データとしてコンビニなどの印刷機で出力するのだそうだ。
そこまで!
でも、わかる。スマホにしろ、パソコンにしろ、データ上で見る文字と、紙に印字された文字は本当に見え方が変わる。
「昨晩は神戸の書店「1003」で、“書いた原稿は一度プリントアウトするタイプ”同士、青山ゆみこさんとトークイベント。話すこと、聞くことをテーマにあちこちへ広がる話。楽しかったです。」
このイベントのことを砂鉄さんがSNSの投稿でそんなふうに書いてくれたことを思い出したのでした。
●
さてさて、フォーエバーに長くなっています。最後にもうひとつだけ。
このようなことをこのレター用に書いていたら、『元気じゃないけど、悪くない』の担当編集であるミシマ社のスミチハルさんが、「登録しました!」というメールをくださって、いつものように爽やかな筆でとても丁寧な感想まで添えられていた(真っ直ぐに物事を捉える、思慮深く、社会意識の高い30代になったところガール)。