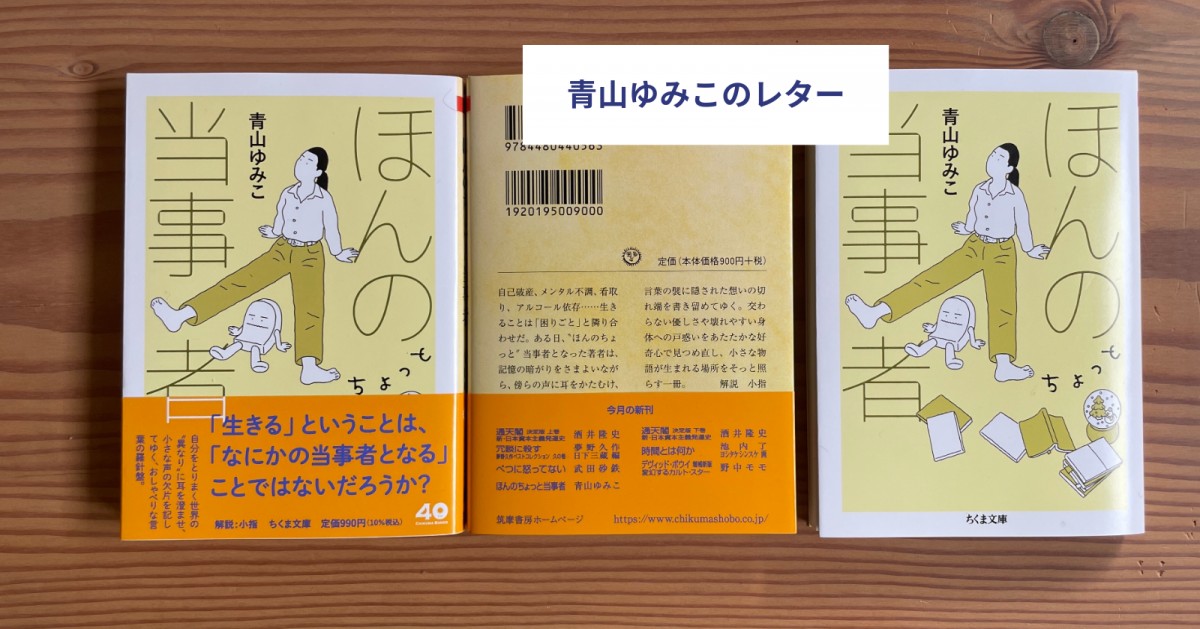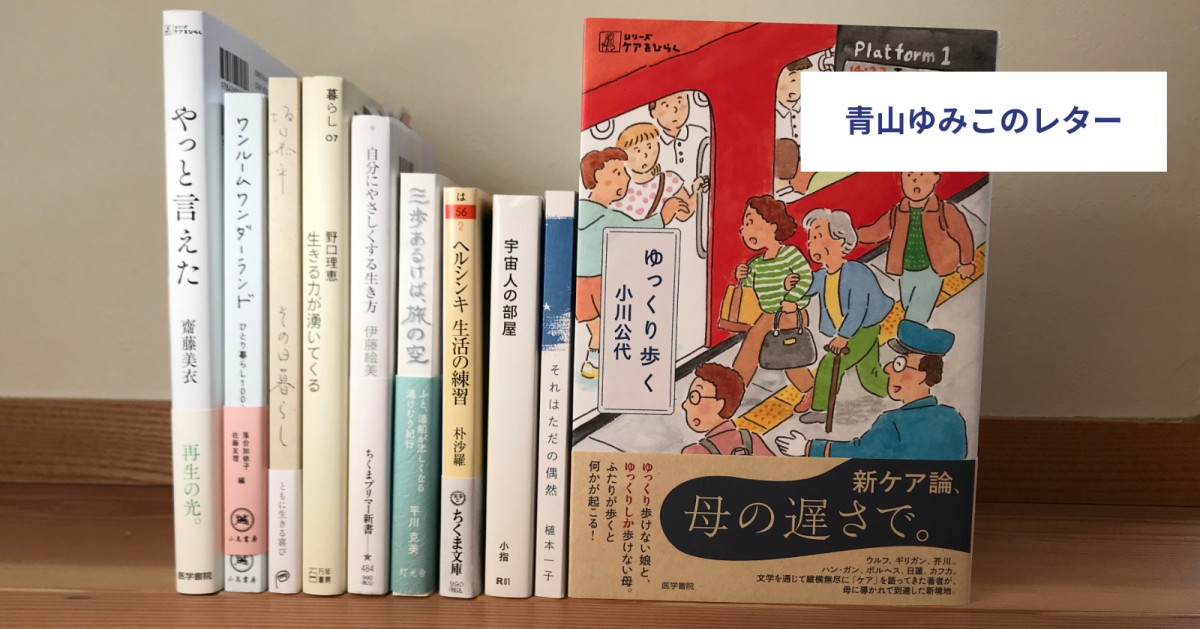年をとるってやっぱりわからない日記2025.1.11〜20
1月11日(土)
オンラインミーティングを終えてお昼(ハコネーゼのボロネーゼ)食べたら、ダッシュでジム。あんまり汗をかかなかったので、シャワーは浴びずに中央図書館に再びダッシュ。帰宅すると23:55締切のレポートが学生から届き始めたので、届いた順番に読んで3名ほどに返信。
パンフレットに感想を寄稿したドキュメンタリー映画『どうすればよかったか?』の上映が神戸でも始まり、元町映画館で見たという人の投稿が、SNSでもよく目に入るようになった。大阪や元町の映画館のアカウントが連日「満席」と告げている。すごいな。関係者の方が公開後の反響を気にされていたけれど、悪くない感想が多いことに勝手ながらほっとする。
統合失調症という病名ではなかった頃に精神を病んだ人を、家族である監督が記録したドキュメンタリー。タイトルどおり簡単な正解のないこの作品にたくさんの人が関心をもつということだけで、心強いというか、うまくいえないけど、やっぱりうれしいような。社会のなかで、「ない」ものとされていたような存在が「ある」と共有されることの意味を思う。
パンフレットでは、精神科医の星野概念さんがオープンダイアローグについて書かれていて勉強になった(わたしは少しだけ触れた)。撮影の背景など、作品の映像だけでわかりにくいことを藤野知明監督が詳細に語っているので、パンフレットもノンフィクション作品のように感じた。
夫が、東山市場の魚屋さんでマグロと剣先いかの切り身を買ってきて、酢飯を炊いて、夜はお寿司。貝屋さんで並んでいた大きな蛤は、出汁をひいて、白味噌を溶いて蛤のお汁。食べることが好きな人が料理担当になると、家の食事が豪華になる。わたしは蟹好きだが、カネテツのカニカマも同じくらい好きで、酢飯があるとマヨネーズを多めにかけて海苔で巻いたカニカマ巻きにする(夫は食べない)。わたしが毎晩飲んでいた頃は、カニカマにマヨネーズをかけて、醤油をちょちょっとつけたのをよくアテにしていた。
そういえばギリシアのキオス島のレストランでシーフードピラウ(ピラフ)を注文したらカニがカニカマだった。世界スタンダードだったとは。わたしが最も愛するカネテツのカニカマと、高級カニ缶とで、カニクリームコロッケをつくってみたことがあるけど、カネテツのカニカマの方が高級な風味のカニクリームになった報告もしときます。そやけど、風味ってなんやろ。ふうみという響きで加味されるもの。
お風呂で村上春樹の『レキシントンの幽霊』の続き。この短編は出だしも秀逸。いつ小説が始まったのかわからない。小説だということすら、つい忘れてしまう冒頭。
1月12日(日)
学生からの感想レポートへの返信の続き。午後は夏休みの宿題追い込み状態でメディア関連本を探しにジュンク堂書店三宮店と、中央図書館をはしご。でも、自分がなにを探しているのかますますわからなくなる。完全に方向が違う、という感触が日に日に増している。なのにわからない。違うということはわかる。
自分が読むべき本に出会うときも、読まないでいい本に出会ったときも、すぐにわかる。たくさん読むことでしか、そのどちらもわかるようにならない。
朝に読んでいるキム・ホヨン『不便なコンビニ』がどんどん良い。ヒーリング小説だなあ。ヒーリング小説といえば、青山美智子『リカバリー・カバヒコ』(光文社)も良かった。カバヒコ本は、昨年9月上旬に千葉の「ジュンク堂書店柏モディ店」で購入したまま積んでいて、少し前に読んだ。
千葉のジュンク堂書店柏モディ店に行ったのにはわけがある。昨年3月に『元気じゃないけど、悪くない』が発売されたあと、柏モディ店さんで4月〜5月に「ミシマ社 青山ゆみこフェア」を開催してくださったのだ(フェアっていっても2冊しかないのに……)。あまりに感激して、いつか行ってみたいと思っていた。そうしたら、初夏頃だっただろうか。閉店することが決まったと耳にした。本屋さんの閉店を知るたびに魂のどこかが削られる。
本当に偶然なのだが、柏モディ店が閉店する日、わたしはたまたま東京出張が決まっていた。閉店の前日、わたしは初めて常磐線に乗り、浅草橋から柏に移動して、ミシマ社の営業ヤマダさんと待ち合わせてお店にお邪魔して、担当書店員さんにも挨拶することができた。書店員さんに「お勧めの一冊」を聞くのは普段控えているが(だって並んでいる本、ぜんぶお勧めでしょうから)、微妙な問いとわかりつつ「記念に!」と手を合わせてお願いして数冊紹介いただいたなかの一冊が『リカバリー・カバヒコ』だった。カバヒコの画像がSNSで流れてくるたび、わたしは柏モディ店の棚を思い出す。
そういえば『不便なコンビニ』は、水嶋書房くずは駅店さんが閉店する前に滑り込んで、たまたま出会った本だ。お店が閉まるというさみしさを黙って飲み込んだ人たちが勧めてくれる本はやさしい。
1月13日(月・祝)
2回目のレター配信。「週の始まり的な日(お休み明けの日)」の夕方配信にします〜なんてお伝えしつつ、いきなり祝日。全然ちゃうやんーと自分でびっくりした。
明日が後期最終授業日だと思いながらレジュメをまとめていると、さみしい。ほんの3〜4カ月の間、週に1回会うだけの学生なのに、この「ぽっかり感」。手紙のやり取りのように、毎回授業前後にかなり親密にやり取りするからだろうとも思うんだけど。
もし自分が小学校の教員で「担任」なんかもってたものなら(中学とか高校でもいいけど)、卒業式では号泣して燃え尽きた灰になる気がする。さみしい気持ちも慣れるものなのだろうか。想像するだけで泣ける。年のせいだろうか。
いくつか宅配便が届く。レターパックは受け取りしないといけないので地味につらい。全て置き配でお願いしたい。朝からずっと家にいる日は昼頃とか、夕方まで顔を洗うのを忘れてる日もある。ぼっさぼさのひっつめ髪に眉毛のないマグショットのような顔に、強度の近視なのでビン底眼鏡が乗っかかっている。冬場は着る毛布でヨレヨレのスエットとか全てを隠しているからまだマシなんだけど、さすがに郵便受けをのぞくときは毛布を脱がないといけないのでわざわざ着替えるほどひどい格好をしている。夫にはどう写っているのだろう。実家暮らしの頃、弟が「姉ちゃん、だましやな」と化粧をするわたしを見て苦笑していた。その頃は若かったのでまだマシだったぞ、弟よ。
夜は、夫が豚肩ロースをトマトと煮込んだもの。ブラックオリーブがごろごろ入ってて「おいしい」と素直に告げる(夫はその30倍くらい自分の料理を自画自賛する)。ワインに合うのだろうなあと思いつつ、特に飲みたくはならない。ただ、飲まないとちょっと手持ち無沙汰になる。そういえば飲まなくなって戸惑ったことのひとつは、「すぐに食べ終わる」ことだ。だらだら食べようと思っても、一瞬で食べ終わるので、だらだら食べられない。これは案外もてあます。飲まない人でゆっくり食事時間を楽しむという人がいたら、どうやってるのか教えてほしい。
飲まないと「食後」が、夜が長い。早く寝るようになった。たいてい10時半を過ぎたらベッドに潜る。
1月14日(火)
後期の授業の最終回。時間めいっぱい。全員の顔を見て、一人ひとりの話を聞けた。皆さん、お疲れさまでした。授業後、数人の学生とお話して外に出ると、クレープのキッチンカーが来ていて、女の子たちが楽しげに並んでいる姿を見るだけで、胸がきゅんとなる。年のせいだろうか。帰宅して、なべ焼きうどん。寒い時期は、あきれるほど昼は鍋焼きうどんばかり食べている。
昨年から読み返していた内田樹先生の『街場のメディア論』。やっぱこれだな(新しい授業の本)と、ほぼ気持ちが固まる。
夕方から歯医者。ようやくかぶせ物の前の土台づくり。ようやく……でも今からかぶせものの型をとって、つけて……もうやめるという選択が自分にはない。走るしかない。メロスの気持ち。
1月15日(水)