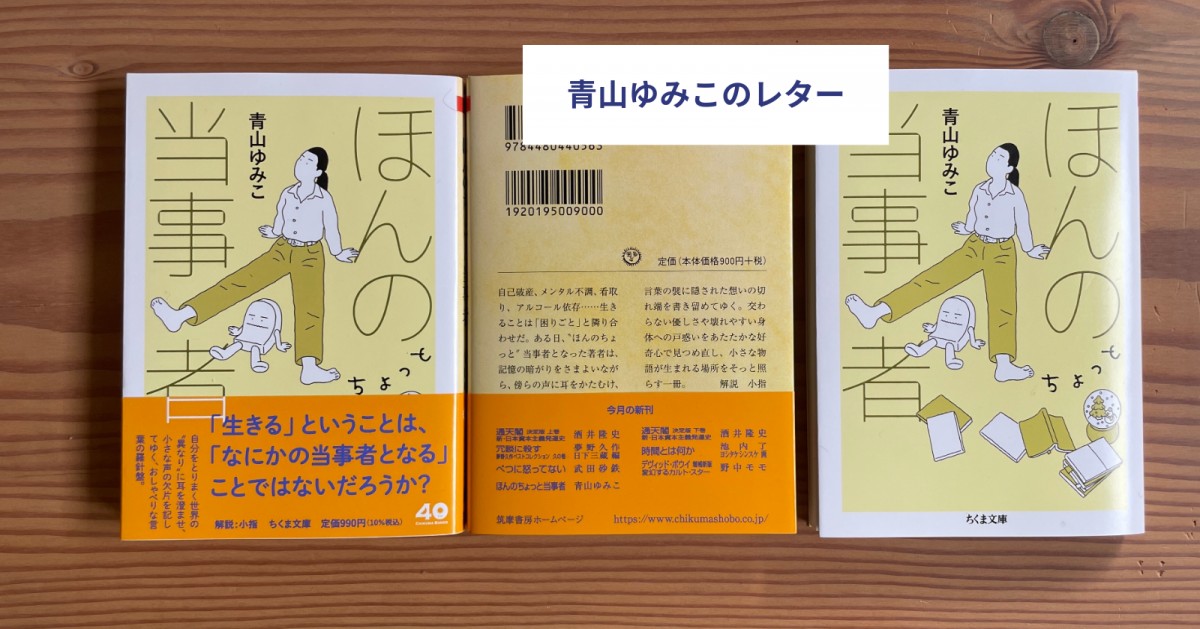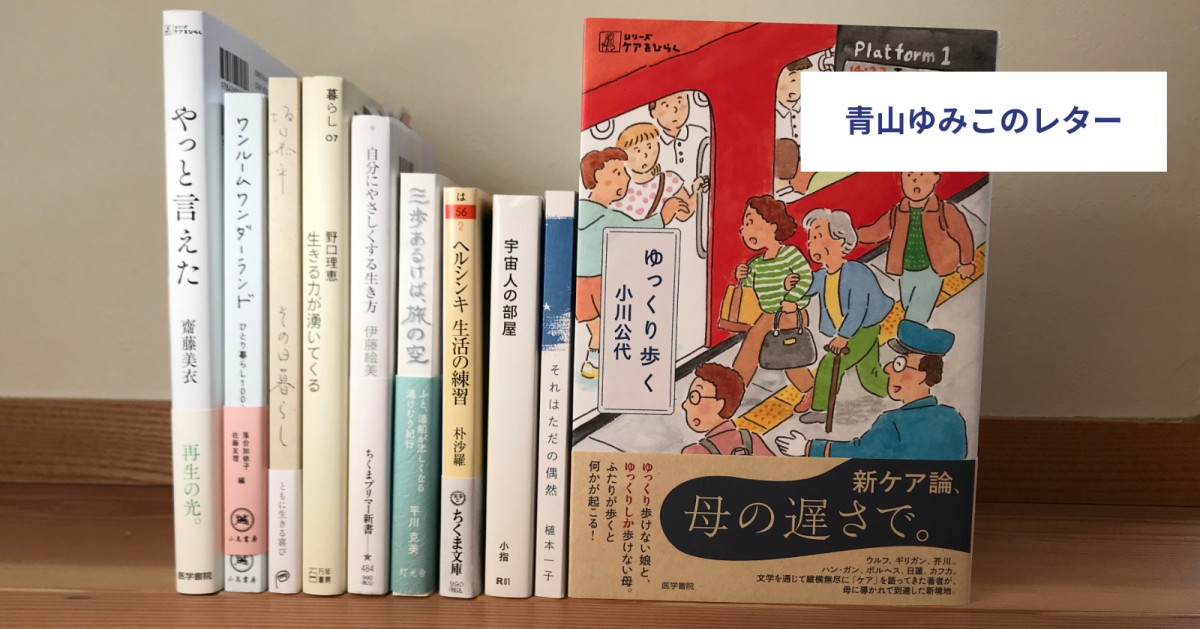ストレスは涙で流して「コーピング」 韓国ドラマでセルフケア
※4/3追記:関連ドラマの主演俳優に関する報道を受け、事実関係が明らかになるまでお名前は控えることにしました。サムネイルも変更しています。
1月に入ってからちびちび見ていた韓国ドラマ『涙の女王』、ついに完走してしまった。久しぶりによく泣いた。悲しい涙だけじゃない、むしろ人のやさしさやあたたかさに涙する……うっかりほっこり泣かされた。見ているわたしが「涙の女王」だ。うぅ。
全16話を走り終えた達成感もあるが、涙でいろんなものが流れ落ちたような爽快感というのだろうか。なにかの禊ぎでも終えたみたいな清々しさだ。
ちょっとだけ作品について説明します。
『涙の女王』は主演の二人もさることながら、ちょい役にいたるまで「あの人が!」「この人が!」と興奮する名脇役揃い。
美貌と財力を兼ね備えた財閥三世の妻ホン・ヘイン(キム・ジウォン)。田舎出身の純朴な性格で、ソウル大法学部卒かつ超イケメンのペク・ヒョヌがヘインと出会い、一見誰もがうらやむ“逆玉の輿”を遂げた。
財閥家に婿入りしたヒョヌだが、人の良さもあってか、「人を使う」ことに悪い意味で慣れきった財閥家の親族たちにええようにこき使われて、さすがにもう我慢の限界。離婚や離婚!と決意し、ヘインに告げようとした矢先、ヘインが治療の余地がない脳腫瘍を患い余命3ヶ月である事を知る……。
そんなところから始まるラブロマンスで、不治の病、記憶喪失、遺産相続、家族の不和、出生の秘密……と「韓ドラあるある」がテテンコ・モリ盛り。同時に、資本主義にまみれたソウルの対局にあるヒョヌの実家のある田舎の場面では、飾らない村の人の素朴さやのどかな生活風景に癒されるヒーリングドラマともなっている(『海街チャチャチャ』みたいな)。もちろん「初恋」「運命の人」的なロマンス要素もたっぷりと。もう「漫画みたい!」だ。
こういうのは韓ドラのお家芸だけど、ほんと話がよくできている。『愛の不時着』も手がけたパク・ジウンの脚本ということもあり、ところどころに『愛の不時着』のパロディ的に張り巡らされた仕掛け、伏線。『ヴィンチェンツォ』のソン・ジュンギがヘインの弁護士役で登場しちゃったりだとか、カメオ出演も言い出せばキリがないほど凝っている。いちいち「おおおお」と興奮しちゃうじゃないか。最終話は、あの『愛の不時着』を超えるtvN史上1番の視聴率を記録したというのも納得だ。
ああ、興奮してつい……(自分がすごい早口になっていました)。韓ドラファンの皆さん以外は、ついてこれないですよね(慌てて後ろを振り返る。汗)。
もう今さら説明いらんかと思いますけれど、わたしは韓国ドラマが大好きで、でも韓国ドラマならなんでもいいってわけではなく、夢中になれる作品だけに夢中になる(当たり前すぎる)。
自分がそんな気持ちになるかどうかは、見てみないとわからない。好みだってある。評判がよくても合わない作品はピンとこない。実は全世界でブームになったという『イカゲーム』はハマれなかった。暴力的なのとか怖いのは苦手なんです……(『ザ・グローリー』はハマったけどトラウマなるかおもた)。
あくまで「自分」にとって「たまらん」「最高」「終わるのがさみしい」作品が名作で、そんな作品に出会えたってときにだけ訪れる幸せを求めて、わたしはネトフリ、アマプラ、U-NEXTの扉を開けては閉めを繰り返し徘徊してしまうのである。
求めているのは、作品との「運命的な出会い」。
本でもきっとそうだと思うけど、ふと出会った存在に理由がわからないまま激しく心揺さぶられる。そんなことに人はなにより感動するのかもしれない。
※ご登録(無料)いただくと、メールボックスにレターをお届けします。わたしの「書く」励みにもなりますので登録いただけますと幸いです。
ドラマに限らず、韓国映画もわたしにはそんな存在だ。自分にとって特別な作品がないかな〜と探すのも楽しみ。見始めて夢中になれたら喜び。そんなふうに「気分が上がる」一つひとつの行為が、わたしにとってセルフケア、ストレスコーピングになっている。
「コーピング」とは「対処する」の意味で、ストレスコーピングとは、「ストレスに対処するためにとる行動」のこと。
『元気じゃないけど、悪くない』(ミシマ社)で書いたが、わたしがメンタル山で遭難してもう下山できないんじゃないかと途方に暮れていたときに出会ったのが、カウンセラーの伊藤絵美さんの『セルフケアの道具箱』(晶文社)。その本でこの「コーピング」という言葉を知ったのです。
本を読んだ少し後、伊藤絵美さんが主催する「ストレスコーピング入門」のオンライン講座が開催されることを知り、自分で自分をなんとかする方法を知りたい、その一心で受講した。その講座のいわば教科書、内容が詳細に書かれている『コーピングのやさしい教科書』(金剛出版)も繰り返し読んだ。
それ以来、自分にとってよさそうなコーピングがあれば意識的に採り入れて、合わないのはどんどん捨てて、合うコーピングだけを御守りのように増やして心のなかにもっている。

例えば締切に追われてつらい、泣きそうと、頭の片隅に漬物石が置かれたように重たい気持ちになっていても、お昼ごはんのお供に30分ほど韓国ドラマを見るだけで、わたしの場合はかなり気分が持ち直す。その間は仕事のことを忘れることができる。つまり、「韓国ドラマを見る」のはわたしのコーピングの一つなんです。
お気に入りの小物みたいに、自分に合うコーピングをたくさんもっているといい。リストにして手帳に書くのもお勧めと、伊藤さんが講座で教えてくれた(コーピングストを書くこともコーピングになるとも)。
とりわけ伊藤さんが繰り返しおっしゃっていたのは「しょぼいコーピングがいい」ということだ。これについては拙著『元気じゃないけど、悪くない』で、こんなふうに書いている。
ーーー引用はじめーーー
例えば、高級な温泉旅館に行くのも良いけど、予算や時間がなく行けないと「できない」気持ちがストレッサー(ストレスを与えるもの)になる可能性もある。ちょっと高めの入浴剤を買う、というのもコーピング。その湯にちゃぽんと浸かる自分を想像するのもコーピング。もちろん夜に良い匂いの入浴剤を溶かしたお風呂に入るのもコーピング。そんなふうに小さなコーピングリストを増やしてもっておけば、日常的にストレスに対処できるようになる、と。
ーーー引用おわりーーー
わたしは神戸の山手で暮らしていて、海の近くの公園まで自転車で10分ほど。晴れて気持ちが良い日には、メリケンパークという波止場近くの公園まで自転車を漕いで、青空に浮かぶ雲の写真を撮る。パシャリという音でぽっと胸があたたまる。嬉しい気持ち。
これを細分化してみると、海を目指して自転車を漕ぐのもコーピング。特に「いいね」がつかなくてもその行為で自分の気分が上がるので、写真をSNSにアップして眺めるのもコーピング。最近はInstagramのストーリーもコーピングに活用して、短い動画を上げてみるのもコーピング。それを再生して眺めるのもコーピング。
繰り返し、これはあくまでわたしの場合。「自分にとって良い」というコーピングが本人にいいのです。
昔は、ナイアガラの滝から飛び降りるような気持ちで高額のブランドものを入手するような興奮や快感を求めたこともあったけど、手に入らないとむしろ大きなストレスを生んだりもする。派手な興奮を手放せるようになったのも、自分にとって悪くないしょぼいコーピングがたくさん手元にあるからかもしれない。その時々で小刻みに選択できるやり方が。
でっかいサプライズで心臓がずきゅんと鼓動したり、テンション爆上がりというのではない、小さな小さな喜びというか、幸せというか。その幸せの理由もわからないし、名前もつかないような行為だけど、心が小さく浮き立つような楽しみが日常にあることで、わたしの一日はまあまあ悪くなくなる。
コーピングについて長々書いていて、思い当たったことがある。
最初に書いた『涙の女王』などのドラマに限らず、韓国映画もそうで、わたしにとって「泣く」というのも結構なコーピングになっている。『涙の女王』はコメディ要素も強いので、大笑いもしたけど、13話以降はずっと泣いてたよなあ。
そうか「ドラマや映画を見る」もコーピングだけど、さらにいうと「ドラマや映画を見て泣く」ってこともわたしにはお気に入りのコーピングなんだなあ。ほとんどセラピーのようにも思える。
●
2017年のことになるが、母を見送ったあと、わたしはしょっちゅう泣いていた。そんなことを思い出したのは、このレターを書いた2月1日は母の命日だったからだ。
8年前は、コーピングどころか、セルフケアなんて言葉も知らずに、ほとんどセルフネグレクトのような状態だったけど、当時もわたしは韓国ドラマや映画を見ては泣いていた。そのことが自分を助けてくれたとも思い当たったのだ。わたしなりのグリーフケアになっていたのかもしれない。
以前『望星』に寄せたエッセイがある。紙の雑誌に書いたものなので、もうあまり入手できないかもしれないので、こちらで再掲します(編集部の担当は吉田文さん)。『望星』は文学的で厚みのある特集がいつも読み応えがたっぷりの雑誌です。

韓国映画のカタルシス
書くことを生業にしている。読むことも日常に欠かせない。
でも、その両方ができなくなった時期がある。三年ほど前のことだ。
二週間の入院で母が旅立った後、私は感情の必要ない「業務」でしか人と関われなくなった。本を手に取っても、書かれた文字はただ眼球を通り過ぎ、言葉として入ってこなくなった。
抜け殻のような私に代わり、一緒に母を看取ってくれた夫が、母の遺した調理器具を使って料理を作ってくれた。食卓には彩り豊かな皿が並び、二人で取る食事は悲しいほどに美味しかった。
お母ちゃんにも食べさせたかったなあ。
夫は、必ずそう呟くのだ。
母は酒を一滴も飲まない人だったが、ウイルス性の肝炎からの肝硬変が進み、加えて肝がんを併発し、最期は手の尽くしようがなかった。壮絶な苦しみようは目にする方が痛みを伴うほどだったが、彼女は決して諦めなかった。十六年という長すぎた父の介護生活に区切りをつけて、一人で自由に生きることを唯一の希望に病床で闘った。そんな母に限られた時間を告げることができず、母に嘘をつき通した。嘘は正しかったのだろうか。わからない。
季節が移り変わっても、脳裏には母の最期の風景が張りついたまま、私はどこへも進めなかった。夫と食べるご飯だけは変わらず美味しかった。
いつの頃からか私たち夫婦には、食後酔ってぼうっとした頭で映画を見る習慣ができた。でも当時、何十本と観たはずのタイトルすら覚えていない。再生ボタンを押すと何かが始まり、終わる。それだけだ。
ある日レンタルショップに行くと、話題作しか見ていない韓流コーナーでふと足が止まった。ハードな殺人ものは夫が怖がるので、『チャンス商会~初恋を探して~』という当たり障りのなさそうな一枚を選んだ。
主人公は地方のスーパーで働く、男やもめの初老の男だ。男尊女卑がきつく自己中心的な男が、同世代の女性に淡い恋をする。その恋を巡り街では小さな騒動が次々と繰り広げられる。
ファンタジーのような柔らかさで、頑固な爺さんと街の人たちの温かさをコメディタッチに描きつつ、時に鋭く現実を突きつける。後に韓国映画の特徴の一つだと知るメリハリの利いた緩急は、見る者を物語に引きずり込む強さと深さがあった。感情表現の激しいお国柄なのだろうか、悲喜こもごもが突き刺さり、胸のあちらこちらが激しく揺さぶられる。
何分か置きに挟まれる食事のシーンも印象的だ。大切な誰かと共にする食事は美味しく、一人で取るご飯は侘しい。食事の風景は多弁に心情を物語る。ぐいぐい引き込まれた。