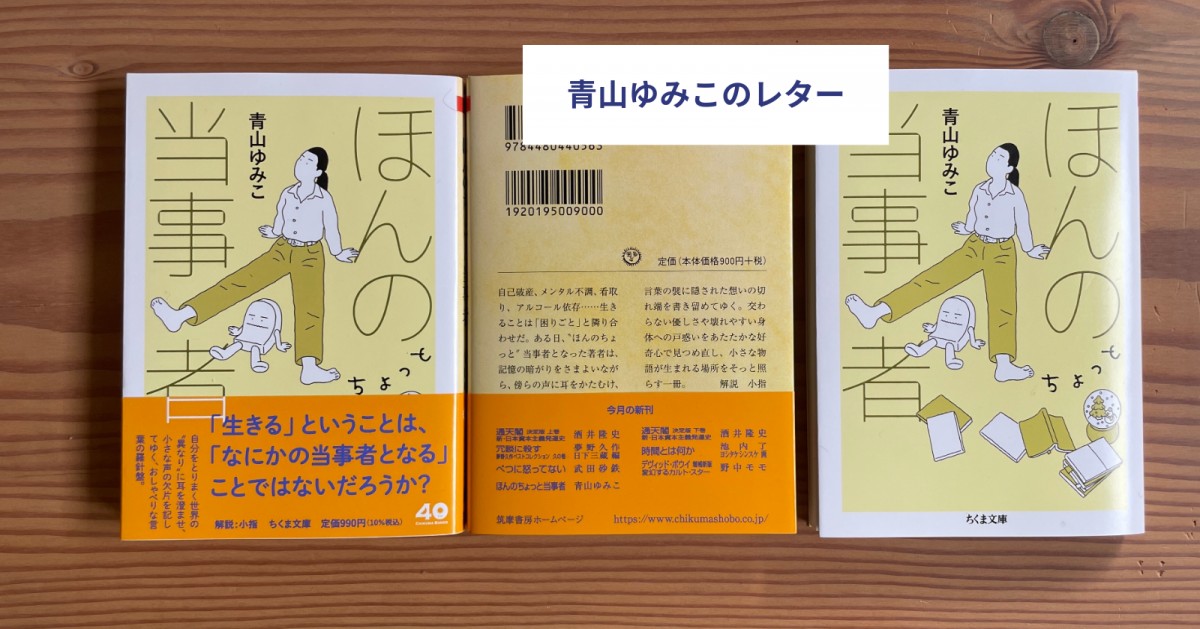漱石と賢治と銀河鉄道の夜
皆さん、こんにちは。9月が早速始まっていますね。暑さだけでなく、いろんな意味でくらくらしています。
さて、唐突ですが『坊ちゃん』の話。いつだったかは思い出せないけれど、確かこの1、2年の間に夏目漱石の『坊ちゃん』を読んだんです。
親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。
皆さん、覚えていることでしょう。あまりに有名な冒頭の一文。
「おやゆずりのむてっぽうで」の響きだけで、なんかもうしゅーっと言葉が脳内に流し込まれまるような。中学の教科書で読んだんだろう。その後、たぶん図書館で本を借りて一回くらいは全文を読んだと思うんだけど、実は全然覚えてない。
なのに、主人公の「坊ちゃん」や、嫌みな教頭「赤シャツ」なんて登場人物とあらすじを知っている気になってるし、愛媛松山の「道後温泉」も知ってて、作中に登場する団子も食べたことがあるような気にさえ(食べたことない)。
それぐらい有名な漱石の初期の代表作。なのに、実はあんま覚えていない小説を、理由も思い出せないが、わたしはなぜかふと読み返したのだった。
気楽に読み始めたところ、驚愕した。 めっっちゃくちゃうまい(誰に言ってるんや)。こ、こんなにうまいとは……。
冒頭の一文から一語たりとも余分なく、テンションは一ミリもダレることなく、展開はひたすら軽快で、ぐんぐん、ぐんぐん進む。
ちょっとしたエピソードとか比喩が、例えば、ものすごく俊敏で華麗な動きの内野手たちが、一塁、二塁、三塁と、しゅっ、ぱしっ、しゅっ、ぱしっとリズミカルに球を回し合ってるような美しさというか、見ていると快感さえ覚えるというか。見事な筆である(だから、お前は誰や!)。 それが最後まで続くんです。
すごいのは、話の行き先は負け試合みたいな感じなのに、それさえ面白く読ませる。なんと……。
夏目漱石を読んできた人には、「はあああ?」となりそうなへなちょこ感想で申し訳なくなるほど、勢いと味のある名文で一気に読了させる小説。それが久しぶりに読んだ『坊っちゃん』だったのでした。
そこからわたしは一気に夏目漱石のあれこれを読みあさったのだった。
とは、まったくいかなかった……。
『虞美人草』とか『こころ』とか『それから』とか『草枕』とか、家の本棚にはえんじ色の背表示の薄い新潮文庫が何冊も並んでいたので(たぶん大昔に買ったんだと思う)、とっかえひっかえ引っ張り出して読んではみたんだけれど。 やっぱ、あかん。全然読めへん。
どれも冒頭の5、6ページほど目を通したあたりで、なんだか気が散って、ついスマホをぴっと点灯させて、Instagramのアプリを人差し指でぴっ。「いいね」ぴっ。
いやいやいやいや、漱石に戻ろうよ。
我に返ってまた本に目を落とし、文字を追うんだけど、全然乗れない。上の空っていうんですか。わたしはそういえば、漱石はいつもこうやって、読もうとしては入れずに何十年という人生だった。
ついに50を過ぎても、近代文学の波に乗りきれないままの生涯を送って来ました。自分には、近代小説というものが、見当つかないのです(太宰風)。
夏目漱石といえば近代文学の本丸。「夏目漱石をとおっていない」わたしは、誰かに聞かれて「小説が好きです」と人に言うときに、どこか後ろめたさを感じることがあった。 文学的素養のなさというか、それはつまり教養のなさではないかと。なんか恥ずかしい気がして。
えー、でも、なんかアカンわけ? 好きな作家読めばええやん。こんな気持ちにさせやがって、「ちっ」。と、勝手に逆ギレのような感情さえ抱くときもあったり(ややこしい)。
わたしは自分のなかで「夏目漱石を読まなあかん」「読んでいる人はえらい」と思い込んでいるんだろうな。愚かだな。いや、ほんとぐぢぐちすみません。
しつこいけれど『坊っちゃん』はすごかったって話です。
ただ、実はその後の話もあります。「またあんなふうに興奮の波が来たらいいな〜」と期待して、時間を置いてから『坊っちゃん』をまた読もうとしたら、もうダメだった。
背中を押されて思わず飛び込んでしまう興奮の扉が目の前でぴしゃっと閉じて、もう開かなかったのです。 一度きりの漱石の奇跡。
本を読むときに、そういう「奇跡」ってあるんじゃないかなと思う。なぜかその日、その瞬間だけ、自分に訪れる奇跡の波。
その波は、そのときの自分にしかとらえられない。そして、読んでみないことには、その波とは永遠に出会えない。しょぼい波にしか会えなかったとしても、毎日沖にパドリングして(本を開いて)波を待つ。それ以外にできることはない気がする。
わたしは毎日本を読むけれど、本を開く度に興奮と歓喜を味わっているわけじゃない。「ああ、これはわたしがわざわざ読まなくても良かった本だな」と確認するために読むんじゃないかと思うときさえある。永平寺の座禅みたいな修業の時間があってこそ、「はっ」という瞬間もあるっていうか(わたしのなかのイメージです)。
話がどんどん逸れてしまった。
「本との出会いの奇跡」についての話です。
再読に限らず、「この書き手の文章には入れないな」なんて思う作家でも、「なぜか入れた!」というときがきたりもするし、好きな小説も、いつでも「好き」なわけじゃない(村上春樹作品はわたしにとってそう)。
だから、おもしろいと思える瞬間を、大事に大事にしたいなと思う今日この頃なのです。
カラマ山が未踏の地のままのドストエフスキーもそうだけど、「いつか読めたら」と思って何度も挑戦するのに、未だ読めない作家が山ほどいる。わたしにとって宮澤賢治もそんな作家のひとりだ。
賢治を語る人がいつも羨ましかった。すごくいいんだろうなあ。なぜか想像できる。たぶん本当にいいんだろうと。でも、わたしは全然入れない。扉が閉ざされたままだ。
ただ、近年、一作だけわたしに特別に関わってくれた作品がある。『銀河鉄道の夜』。それも本で読んだのではなく、人形を使った朗読劇の舞台を、オンラインで映像として見た。2021年の夏のことだった。
当時、わたしは難攻不落に思えた深いメンタル山で遭難中だった。
仕事場という体で借りた、自宅とは異なる「一人で引きこもるための部屋」で、不安の負のループにぐるぐると巻き込まれながら、とにかく身体を休めるのだと、ひたすら「なにもしない」を全力でしていた頃だ。