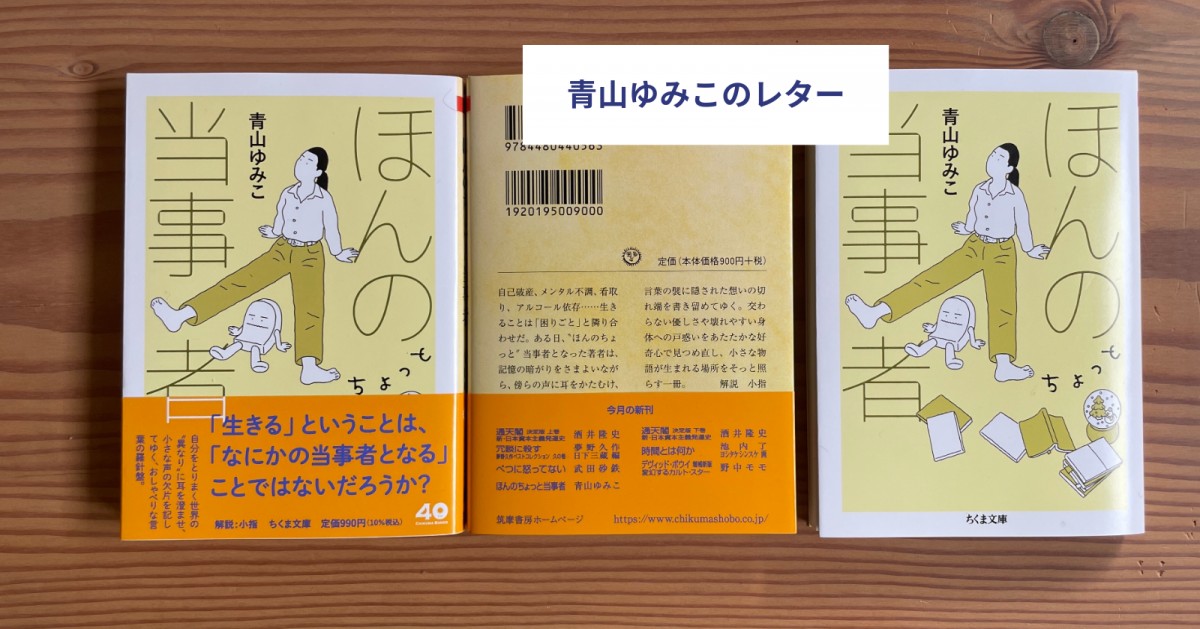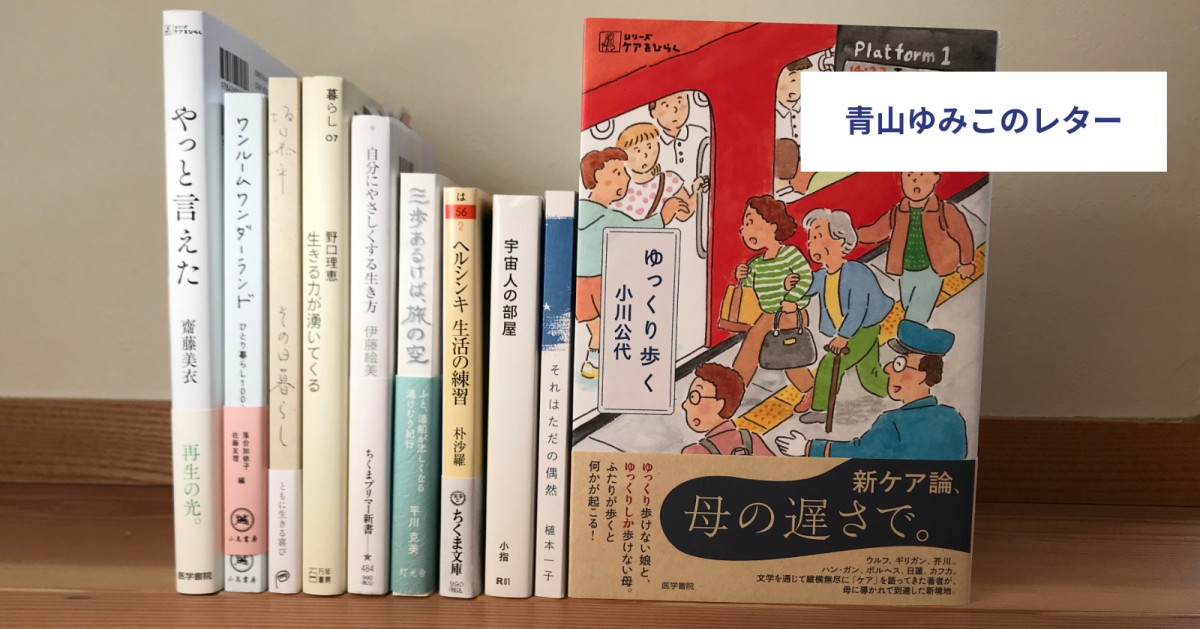神戸からの長い手紙(前編)。阪神淡路大震災から30年。思い出す人の顔
NHK「100分de名著」は、古今東西の「名著」を100分で読み解く番組だ。この1月は、精神科医である安克昌先生の著書『心の傷を癒すということ』がテーマ本。
わたしは配信でまとめて見るのを楽しみにしていて未見だが、神戸に暮らす身には、あの地震が起きた1月という時期に、安先生のこの本が特集されるというだけで、心がやわらぐような気持ちになっている。
安先生のお名前は、飲み友達から聞いて知った。同い年で、親戚でもないのにたまたま同姓の男友達だ。気づけば20年ほどの付きあいになるが、知り合ったのはひょんな偶然だった。

※ご登録(無料)いただくと、メールボックスにレターをお届けします。わたしの「書く」励みにもなりますので登録いただけますと幸いです。
2004年、わたしは『Meets Regional』という月刊誌の編集部に在籍し、5年目くらいの中堅どころとしてしゃかりき働いていた。30を過ぎて仕事が面白い時期でもあった。
当時、『Meets』誌では思想家で武道家の内田樹先生が「街場の現代思想」という超人気連載を寄稿くださっていて、わたしももれなく大ファンで、ブログも熱心に読んでいた。
内田先生は「どこにもいかないで家にいるのが好き」とよく書かれているが、むしろ逆で非常にフットワークが軽く、この頃も神戸の三宮あたりのワインバーにもよく顔を見せてくれた。例えば、編集者との打ち合わせや対談などにも「じゃ、Re-setでやりましょう」と気軽にワインバーに足を運ばれる、なんて感じで。
6月のある日、晶文社の安藤聡さんのセッティングで、作家の田口ランディさんと内田先生が「Re-set」で会うと小耳に挟んだ。「Re-set(リセット)」というのは、橘真(たちばなまこと)さんというシニアソムリエがカウンターに立つワインバーだ。店は三宮の超駅前のビルの一角にあった。
橘さんは、わたしより一回りほど年上で、ソムリエとして輝くような経歴を持ちつつ、ワインに限らず博学多識、神戸の街でも有名な人だった。
ヨットレースが趣味とあり潮風にあたりがさがさっと日に焼けたきつね色の顔は、笑うと目尻によるしわがチャーミング。朗らかだが非常にマイペースで、魅力的な人の多くがそうであるようにクセも強い。
社会を読み解く独自の視点が興味深く、なにかモヤモヤするニュースを見聞きすると、「橘さんならどう考えるだろう」と取材でもするように話を聞きに走ったりするような、大好きな街の先輩の一人だった。
「Re-set」の前身となる「ジャック・マイヨール」という隠れ家みたいなワインバー時代から、橘さんが立つカウンターには、自ずと街の妖怪みたいな人が夜な夜な集まって、仏や伊のややこしい(否、こだわりの強い)のシェフが料理哲学を語ったり、構造主義とかポストモダンとかの論客が侃々諤々。とはいえわたしのようなただの酒飲みも許してもらえるような、懐の深い街場のサロンのような場所でもあった。
2001年に内田樹先生の『ためらいの倫理学』が出てからは、「ため倫」に感銘を受けて、内田先生の熱心な読者が、同じく熱心な読み手である橘さんの元に集まるようになった。橘さんがそれを「街レヴィ派(街のレヴィナシアン、レヴィナス派の略)」と呼び、面白がっていた。
神戸に住んでいてラッキーだとつくづく思うのは、当の内田樹先生がしばしばこの「Re-set」に姿を現すので、ワインバーのカウンターで貴重な講義を受けられたことである。
例えば映画の話をしていたら、『男はつらいよ』の寅さんって……みたいに始まったお喋りが、いつの間にか「家族」を読み解く哲学講義になっていて、わたしたちは「なるほど」「そうだったのか!」と腑に落ちて頭をクラクラさせたり(酔いが回っているのもあるかもしれないが)。
常連である街の妖怪のなかには「ちょっとちゃいますわ、僕に言わせたら」と持論を展開する人もいる。すると、内田先生は「うんうん、へええええ」と心から面白そうに聞き入っている。
そんな姿さえ、街レヴィ派のわたしには、「真似したい大人の姿」として目にしていたように思う。その人が真っ直ぐに話すなら、まず興味を持って人の聞くってことを。

『Meets』誌の連載はのちに『期間限定の思想「おじさん」的思考2』に収載。『私家版・ユダヤ文化論』(2006)は第6回小林秀雄賞受賞、『日本辺境論』(2009)は第3回新書大賞受賞
●
話は2004年4月に戻る。
田口ランディさんと内田先生が二次会で流れてくるという「Re-set」に、わたしも仕事終わりに立ち寄ると、いつものように橘さんが、なにか愉快なことでもあったような表情で迎えてくれた。
内田先生が「青山さんもどうぞ」と声をかけてくれ、晶文社の安藤さんがにこにこ笑っているテーブルに同席させていただくと、ランディさんの隣には見知らぬ男女がいた。自分の友人で臨床心理士のナカタニさんと、彼女の同僚である精神科医のアオヤマさんですと、ランディさんが紹介してくださった。
内田先生の隣にはわたしも親しくさせてもらっているドクター佐藤さんが先に合流されていて話はすでに佳境、わたしには難解な内容も多かったけれど、橘さんが選んでくれるワインは最高に美味しいし、賑やかで楽しい夜がわちゃわちゃと更けた。
さて、この日「Re-set」でたまたま同席した精神科医のアオヤマさんこそ、わたしに安克昌先生の存在を教えてくれた人だった。
彼は数日前、場所を確認するために「Re-set」という店名をインターネットで検索していたら、わたしが当時書き散らしていた「いや、ほんのちょっとだけ」というブログに辿りついたそうだ。
「同姓」という偶然を彼も面白く感じたらしく、他の記事も少し読んだところ、どうやら世代も近そうなことを知り、わたしがあの夜、遅れて「Re-set」の扉から入ってきた姿を見たときに、「あれが青山さんだな!」とブログで読んでいたイメージとつながったのだと、後になってから聞いた。
そんな不思議なご縁もあってか、それ以来、わたしたちは飲み友達になった。
アオヤマさんはなんていうか、わたしが勝手に抱いていた「医者っぽさ」がない。圧がない。まあ、そもそも仕事の話をしないので、医者の顔を見たことがないからかもしれないけれど。むしろ一見「なにをしてる人かわからない」この青年は、鷹揚な物腰で、笑顔が爽やかで、誰かの提案に「お、いいですね〜」とすぐのるご機嫌なゆるさをもっていた。
同じ時代を生きてきた同い年ならではか、本や映画、音楽の話も好みは違っても話が合った。飲むペースも近かったから、よく飲んで話をした気がするけれど、なんの話をしていたのかこれを書きながらもまるで思い出せない。二人で話すというより、橘さんをはじめ、好きな店主がいるお店で会うものだから、なんとなくいつもみんなで街の、人の話をしていたような気がする。
そんななかで、アオヤマさんから仕事の話が出ることはないし、精神科医という仕事を知らないわたしは、なんとなく「この人も自分と同じ接客業、サービス業の人だな」と勝手に感じていた。
街の雑誌をつくっていると、もうほんとに面倒というか、ややこしい人に出会うことが多かった。同時に、「こんな面白い人がいるのか」と衝撃で興奮したりもする。それが同じ一人の人に対して起きることもある。問題ごとも頻発して、そんな人たちにいやおうなく「巻き込まれる」。人間の一筋縄でいかなさ、おもしろさ。
わたしは時に「なんであの人は……」などと愚痴をこぼしつつも、なぜかそんなことや人たちに強く惹かれてしまうのだが、アオヤマさんはわたしの話をいつも興味深そうに聞いても特に何も言わずに、美味しそうに水割りなんかを飲んで笑っている。この人も相当な街好き、人好きだな。変わった人だ、面白いぞ。
本の話をしていた時だろうか。アオヤマさんから名前を耳にしたのが安克昌先生だった。アオヤマさんは神戸大学医学部附属病院の精神神経科で、安先生とご一緒していた時期があるという。世間でいう関係性だと、「恩師」のような存在なのかもしれない。でも、そういうありきたりな言い方では二人の関係を耳にした記憶はない。
2000年に早逝したという安先生が、彼にとって特別な存在であることは、安先生を語る言葉の気配から伝わってきた。安先生が不在であることの悲しみも、深く。『心の傷を癒すということ』は知り合いの本のような気持ちで読んだ。
中井久夫先生の名前も、神戸の街の話をしていて、アオヤマさんから耳にした覚えがある。わたしが西の郊外の垂水出身で、中井先生も垂水に住んでおられたからだっただろうか。お二人の本は、同じ街の人の「語り」として、自分に言葉が入ってきたことを思い出す。
もしかすると、全く知らずに手に取っても、異なる街に住んでいる人にもそんなふうに届く「声」のお二人だろうとも、今は思うのだが。

わたしが新卒で入社したアパレルメーカーで働き始め、服飾デザインをしていた社会人2年目の終わり頃、1995年にあの地震が起きた。ポートアイランドに本社があったので、公共交通機関がストップしている間は、垂水の自宅から何時間もかけて車で通勤した。
まだ焦げたような煙の匂いが漂っている新長田界隈。倒壊したビルで塞がった大通りや陥没した幹線。そこを迂回して脇道に入りこむと、かつてそこが住宅地だったことを積み上がったがれきでしか想像できないような「街並みのなくなった」街。折れてぶら下がったままの信号機。避難先を記した貼り紙……。
毎日、毎日、生活があったはずの、かつて街であったものを運手席のフロントガラス越しに見ていたのは何か月、いや、何年なんだろう。記憶が混濁してわからない。
そのアパレルでは4年半ほど働いて、わたしはいくつかの理由で会社を辞めて、半年ほどぶらぶらした後、たまたま好きでよく読んでいた雑誌を発行している出版社の求人を新聞広告で見て応募して、「作文課題が一番面白かったから」と面接に呼ばれ、「経験者募集だから社員には採用できません」と不合格を言い渡され、なのに「神戸の街に詳しいから」とアルバイトとして採用された。その後、契約社員になり、正社員になり、副編集長をしばらく務めてフリーランスになった。
編集者になりたいなんて考えたこともなかったが、その雑誌の街と人の記事を読むのが好きだったから興味を持ったのだと思う。地震ですっかり変わった街で、戦後のごちゃごちゃとした港町ならではの話や、震災後すごい速度で風景が移りゆく街の話を聞くのが面白くて、雑誌の仕事に夢中になったのだと。
わたしは街を歩き回り、人と会い、お願いごとをしたり、面倒な相談を受けたり、振り回されたり、嬉しく驚かされたりしながら、こういうのはやっぱり接客サービス業だと感じて、どんな仕事より面白く感じた。面白いと感じたこと、聞いた話をひたすら書いた。
(後編につづく)
後編はアオヤマさんをはじめ、(まわりまわって)安克昌先生や中井久夫先生がリアルにわたしを助けてくれた……というお話です。
◉ ◉
レターの感想や読んで思い出したことなどあれば、SNSでぽそっと呟いてもらえたら嬉しいです。読んでもらってることが伝わってくると、ほんとしみじみ嬉しいものだから。
メンバー登録いただいてメールレターで読んでくれている皆さん、本当にありがとうございます。
◉ ◉
※このレターは月4本ほどの配信予定です。メンバー登録(無料)すると全文読める記事をお届けします。このレターは有料のサポートの方のご支援でお届けできています。わたしの「書く」励みにもなります。可能な方はご検討いただけますと嬉しいです。
【おまけのお話】今回のレターのタイトル「神戸からの長い手紙」は、1974〜1984年に発行されていた『SAVVY』の前身となる雑誌『神戸からの手紙』と、神戸出身の作家・村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』の「間宮中尉の長い手紙」にかけています。自分で説明するのもなんですが……。
すでに登録済みの方は こちら