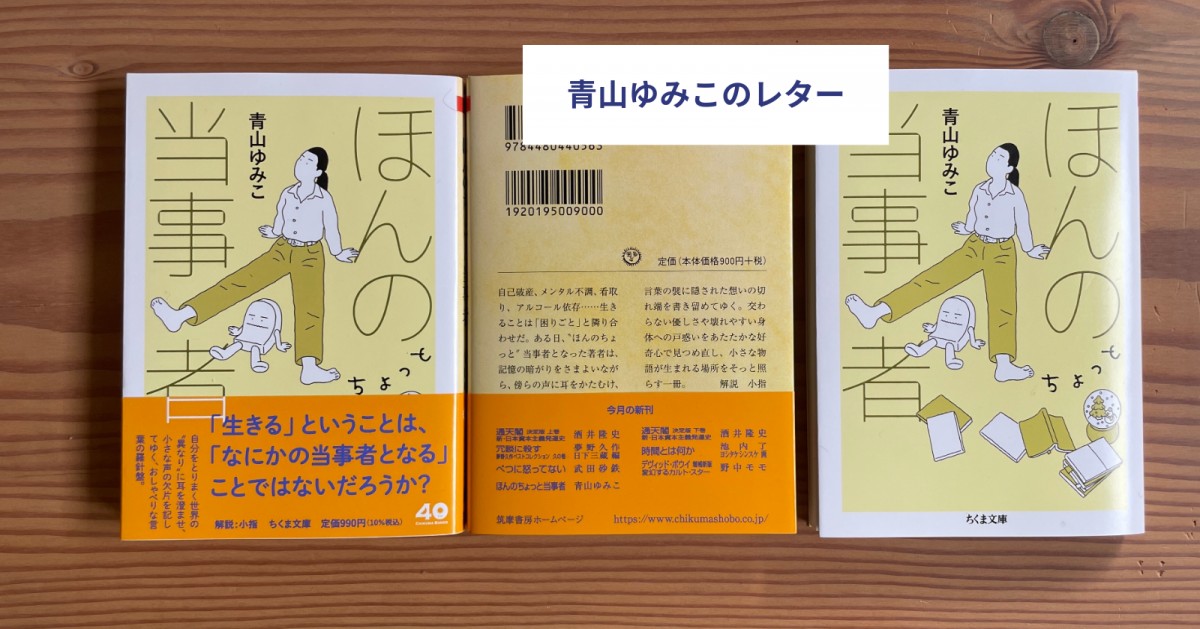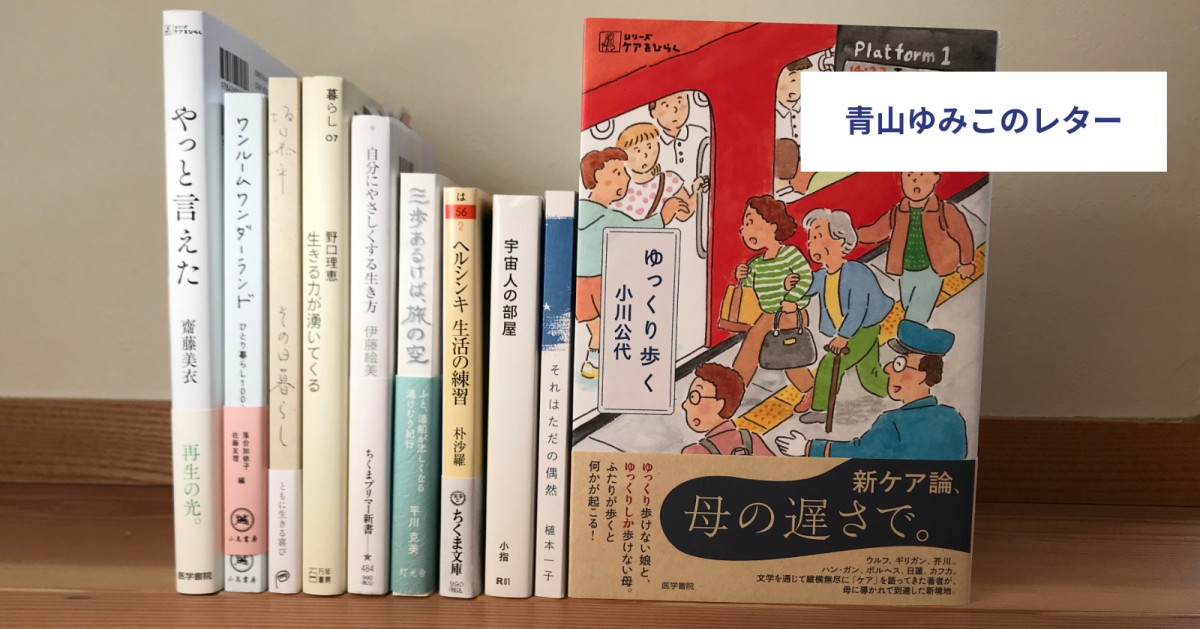神戸からの長い手紙(後編)。震災30年。映像、文学、物語の力
※前編はこちらから読めます
昨年、『元気じゃないけど、悪くない』(ミシマ社)という本を上梓した。
わたしがわけのわからない不調のどん底から、トライ&エラーを繰り返しながら試行錯誤して心身のリハビリする3年のプロセスを記録したような一冊だ。
ヨレヨレのわたしに併走するように登場する「心の主治医」のT先生は、実はアオヤマさんの先輩にあたる人である。中井久夫先生や、安克昌先生がおられた神戸大学医学部付属病院の精神神経科時代の。
2020年の夏頃、自分のろくでもない飲酒癖や家族間の問題に悩んでいた。ひどい不眠も気がかりで、人生全般に途方に暮れていたとき、友人としての会話のなかでアオヤマさんからT先生の名前を聞いた。
本には書いているが、10数年前、夫がパニック障害でしんどかった頃、助けてくれたのもこのT先生だった(夫とアオヤマさんも飲み仲間なのです)。
お酒と睡眠の問題で通い始めたT先生のクリニックだったが、2020年の秋には、さらにどかんがつんといろんなことがあり、ちょっと落ち着いたと思った年の瀬のある日、わたしは心も身体もポキンと折れて、動けなくなってしまった。
自分があらゆる面でコントロール不制御となる苦しさは、知識として見聞きして想像していたものを遙かに超えて、かなりきつかった。
そんな自分からもう逃げて、楽になりたいから希望をもって人は死を選ぶのだ。最もしんどかった瞬間にそんなふうに「わかった!」「すごい」なんて思う自分が怖くなって、自分をどうにかしたい一心でT先生の診察室に駆けこんだ日のことを忘れない。
「もう大丈夫。あなたは自分も誰かも傷つけないよ」
わたしの目を真っ直ぐに見てそう教えてくれたT先生。一時的な軽い躁と不安障害の診断を受けた。
その後はむしろ鬱のような状態で、息を潜めるように自宅に閉じこもって暮らした時期、少しずつ外に出始めた頃……小さな小さな一歩と転機があって、いまはこうして、元気いっぱいじゃなくても悪くない人生を、どこか他人事のように眺めて、面白がれるようにもなっている。
これは回復なのだろうか。うーん。わたしには回復とはまた違うように思う。
『心の傷を癒すということ』は、自らも被災した安克昌先生の体験、目にした風景、出会った人たちについて被災地から語られた手記だ。
同時に、ケアする側の人の苦しさ、もどかしさ、やりきれなさ、無念のようなものも安先生の声で強く届いていたことが印象的だった。
ケアされて心を癒す人には時間が必要で、それに併走する「ケアする人」にも同じことが言えるのではないだろうか。
おおげさではなく命の恩人の一人であるT先生のクリニックには、今も毎月通って相変わらずな話をすることで御礼にかえている(つもりです)。T先生とご縁でつなげてくれたアオヤマさんにも深く感謝している。本人に言うと「えー、いやいや」なんて逃げられそうなので、ここでこそっと書いています。本当にありがとう。
誰かに御礼が言えること、それはわたし自身の心も癒してくれる小さなよきものになると感じている。
※ご登録(無料)いただくと、メールボックスにレターをお届けします。わたしの「書く」励みにもなりますので登録いただけますと幸いです。

2022年10月発刊『安克昌の臨床作法』(日本評論社)。皆さんが安先生を語り合うグリーフケアの場のような一冊に感じた。冒頭の胡桃澤伸さんの「刊行に寄せて」で「安克昌を自由に語る」の意味を知って読むと、わたしまで泣きそうになった。松本俊彦先生のご寄稿もすごい迫力です……
『元気じゃないけど、悪くない』を読んだ方から、「(良い先生とつながれた)青山さんは運が良かった」というようなことを言われるときがある。確かにそうかもしれない。けれど、なんだろう、神戸にいるとそれだけでもないように思うのだ。
街でばったり会った知人から「心のクリニック」について聞かれることが少なからずある。「咳がひどくて、きちんと診てもらおうと思うんだけど、いい先生いないかなあ」みたいな感じで。
神戸では「人の心には傷がつく」ということが、あの地震以降、街全体で共有されているような感覚がある。心が強くないといけないとか、精神科にかかったらダメだとか、そんなふうに思わない土壌。大きく荒れてしまったからだと思うと複雑ではあるが、時間がかかってもまた土が育つという事実を見てきたことは、わたし自身の大きな希望ともなっている。
わたしが心身の不調に陥って、少しでもよかれと思う行動にトライしてはエラーを繰り返すうちに、「人生はやり直しができないけれど、生活は立て直しができる」と感じるようになった。
いま書きながら思い当たったのだが、被災した神戸の街が以前とは異なる姿で立て直しをしてきた、それを見てきたから、わたしはそんなふうに感じるのではないだろうか。
大きく損なわれたものが元通りに戻るということは残念ながらない。いやというほどその現実を目にし続けた30年だ。でも新しいやり方で始めることはできると知った30年でもある。
回復とは、元の自分に戻ることではなく、自分にとって悪くない、新しいやり方を始めること。
安先生や中井先生の本を読み返すと、そのことが繰り返し書かれていることにも気づかされる。
神戸には、荒れた土地を耕して、新しいやり方で生きることへと導いてくれたような存在がいる。精神科医に限らず臨床心理士や、精神保健福祉士……たくさんの心のケア従事者が。また、それは精神医療の分野に限らない。文学や物語も神戸に暮らし続けるわたしを助けてくれている。
●
安克昌先生の著書が原作となったNHKドラマ『心の傷を癒やすということ』を初めて見た2020年1月、わたしはテレビの前で何度も嗚咽した。
その頃は地震から20数年が経ち、わたしのなかでかなり遠い記憶になっていた、と思っていたにもかかわらず、こみ上げて止まらない涙、引き裂かれるような胸の痛み。そこまで感情が揺さぶられることに自分でも驚いた。
2020年はその直後にコロナが始まって、緊急事態宣言やら巣ごもり生活やらで、街から引き剥がされるような日々に投げ込まれた。うまくいえない、なんだろうこの息苦しさは……そんな気分に戸惑ったとき、わたしは再び安先生や中井久夫先生が傷ついた街や人について書かれた文章をすがるように読むようになった。この人たちの話は安心して聞ける。そういうふうに感じて。
話が行きつ戻りつして恐縮だが、『中井久夫 山口直彦 追悼文集』(神戸大学精神神経科医局会・同門会 編)の話をしたい。

表紙:中井久夫先生による『分裂病のはじまり』(クラウス・コンラート著、中井久夫・山口直彦・安克昌 訳)についての手書きのメモ 装丁:慈憲一(六甲技研 naddist)
2023年5月に発行されたこの追悼文集は、いまでいうZINEのような冊子で、アオヤマさんが当時医局会の代表をしていた流れで、わたしも少し編集のお手伝いした。
制作過程で手元に集まるご寄稿に目を通していると、中井久夫先生、山口直彦先生のお人柄が伝わってくるエピソードが多く、笑ったり、しんみりしたり、ぐっときたり(しみじみ贅沢な仕事だった)。
なかでも山口直彦先生の「飲みにいこかエピソード」を書かれていた方が多く、神戸のあちこちの店の名前が出てくるどの話も、思わず頬がゆるむような人の関わりのぬくもりに満ちていた。わたしはそのときに山口直彦先生のお名前を初めて知ったのだが、読むだけですっかりファンになり、お会いできなかったことを残念な気持ちに感じた。
そして、なんだか大きく腑に落ちた。
わたしが若い頃から、橘真さんがいる「Re-set」をはじめ、街の先輩方や友人が立つカウンターのあちこちに毎晩のように通い、そこでたまたま出会った誰か(アオヤマさんのように)と話をしたり聞いたりしていたことが、自分をどれほど助けてくれていたのかと。
安先生の原作の映像作品でも、街に出るシーンがよく描かれている。それぞれが「なにか抱えているものあるよね」「あるもんだよね」って、まるで日常の中で心の手当てをしあっているような風景が。
橘さんは「Re-set」を畳んでから、淡路島に移住して農家になった。ワインをつくる葡萄を育て始めた。という矢先、病に倒れ、闘病を経て2017年に旅立った。まだ50を過ぎたばかりの若さだった。
闘病の時期、抗がん治療のため入院していた神戸の大学病院は、うちから自転車でも通える場所だったので、わたしは橘さんが好きそうな本を抱えて何度かお見舞いに行っていた。
あるとき、病室をのぞくと「あ、青山さん。さっきアオヤマ先生が来てくれたわ。あおやま、あおやま、ってややこしいなあ。ははは」なんて愉快そうに笑っていた。科は異なるが、その病院はアオヤマさんの職場でもあったからだ。
でも、アオヤマさんとわたしは一度も病院では鉢合わせすることはなく、久しぶりに会ったのは淡路島で行われた橘さんの葬儀の会場だった。言葉がなかった。
神戸までの帰り道、アオヤマさんと夫とわたしの三人は、橘さんがいかに変わった人だったかを話して笑った。大切な人を失ったとき、なにもできないけれど、でもその人の不在を語り合うことはできるのだと思う。
内田樹先生による橘真さんの追悼文はこちらです。
●
今年に入ってから17日まで、あの地震から30年が経つのだと、毎日のようにニュースが伝えていた。24歳の終わりに地震を体験したわたしは、気づけばもう震災後の人生のほうが長くなっている。
「記憶を風化させてはいけない」という言葉を、この1月もよく見聞きした。社会としては間違いなくそうだけど、個人としてはどうなんだろう。すぱっと言い切るのはむずかしい。
というのは4年前の2021年、わたし自身の体験による。
前述したように、当時心の調子を大きく崩していたわたしは、その年に限って1月17日が近づくと、20数年前の地震当時のあれこれを、これ以上なく生々しくリアルに思い出してしまった。
年々記憶が薄れていて、地震の記憶が他人事にでもなっていくような自分に対して寒々しいような、やりきれなさがあったのに、心が脆くなったときに、その記憶がまるで自動再生される映像でも見るようにくっきり浮かびあがったのだ。
それは記憶というより「たったいまの現実」としか思えない状況としてわたしに降りかかり、息ができないほど全身を圧迫して、胸は引き千切られるんじゃないかと思うほど痛んだ。自分は何一つ忘れていない。パニック発作が頻発して、まさに安先生が書かれているPTSDとはこれか、と理解した。あまりに苦しくつらい出来事を、そんなふうに思い出すことが自分に良いとは思えない。
忘れたくない人は忘れないでいい。でも、毎日を、この一瞬を生きるために今は忘れたいって人は、生々しい記憶にそっとベールをかけて見えないようにしていてもいいんじゃないかって思う。
●
忘れたくないのに思い出せなくなった。そんな人もいるかもしれない。その悲しさも身に覚えがある。
これはわたしの場合だが、映像を目にすると自分でも驚くほど記憶が蘇る。ドキュメンタリーだと生々しいけれど、丁寧につくられた物語は、心の深いところにそっとふれてきて、悪くない距離感で思い出すことを助けてくれる。『心の傷を癒すということ』や、同じくNHKドラマから映画化された『その街のこども』は神戸の地震・震災を描いた映像のなかでも、とても丁寧に記憶に触れてくる作品だと思う。
わたしはこの2作を「心のアーカイブ」のように感じている。普段は自分の外に置いておきたい震災の記憶を、思い出したいとき、思い出しても大丈夫なときに見る。そんなことができる厚みのある映画だ。
今年の1月17日から公開が始まった『港に灯がともる』は、『心の傷を癒すということ』の演出を手がけた安達もじりさんが監督した映画で、プロデューサーとしてクレジットされている安成洋さんは、安克昌先生の弟さんである。
連作ではないが、『心の傷を癒すということ』と深いところでつながった安克昌先生のシリーズ作と受け取った。
主人公は、地震の直後に生まれた、地震を体験していないはずの灯(あかり)。
しかし彼女の生い立ち、環境を見ていると、彼女も「被災した」としか思えない。映画を見てもらえたらいいなと思うので詳しくは書かないが、地震を直接体験した人、あの日を覚えている人だけが「被災者」ではないのだと、初めて強く感じた作品だった。
灯を演じた富田望生さんは福島いわき出身だとお聞きしたが、すさまじく迫る演技で、わたしが心の不調の渦中なら、パニック発作を起こしたかもしれないと思うほどの熱演だ(なので無理せずに見てほしい)。
なかなかに重たいテーマが複雑に絡み合う物語なので、わたしはまだこの映画についてうまく言葉にできないでいるが、「背負う・背負わされる」こと、「ケアする人は誰にケアされるのか」ということも考え続けている。
●
1995年のあの朝、自宅にいたのは両親とわたし3人だった。今はもう父も母もいない。震災後の10年、15年というまだ街に残る傷あとが生々しい時期に、親しくしていた人たちの何人もが鬼籍に入った。橘さんもその一人だ。
灯台のように神戸を照らしていてくれた中井久夫先生も一昨年この世を去った。近しい人も、遠くから存在を感じている人も、その人の不在には心が揺れる。
生き続ける限り、この先もわたしは誰かを見送らねばならない。
いなくなった人の話をして、笑ったり泣いたり、思い出したり、忘れたりしながら生きるわたしたちのために、街はあるのだと思う。
わたしが笑ったり泣いたり、思い出したりするから、街はあるのだと思う。
思い出せないとき、思い出したくないときがあっても、街がある限り、やっぱりわたしは忘れたりなんかしない。
映像はもちろんだが、例えば村上春樹の『神の子どもたちはみな踊る』のように、神戸の地震について直接的に描かれていなくても文学的にそっと触れてくれる作品もある。
『神の子ども〜』は橘さんもわたしも大好きな短編集で、あるとき、「Re-set」をしめたあと(25時閉店)、「モナリサ」という北野のカフェバーで朝まで話しこんだことがあった。この短編集を手に取ると、今でも橘さんを思い出す。
橘さんはそういえば、文学が自分を助けてくれることを教えてくれた人でもあった。振り返ってみれば、街で話をしているなかで出会った安克昌先生や中井久夫先生にも、直接お会いしたことがなくとも書かれた文章に助けていただいている。
わたしが不調のどん底にいた3年間も、児童文学やコミックも含めてたくさんの本に救われて、転機をもらい、励まされた。文学や書かれた言葉の力をわたしは強く信じている。
物語がもたらす希望、契機をわたしは疑わない。時に効きすぎて痛みを伴ったとしても、深い思いを込めて丁寧につくられた作品はそんな力を持っている。『港に灯がともる』も誰かにとってそんな存在となることを願う。
(おわり)
◉ ◉
レターの感想や読んで思い出したことなどあれば、SNSでぽそっと呟いてもらえたら嬉しいです。読んでもらってることが伝わってくると、ほんとしみじみ嬉しいものだから。メンバー登録いただいてメールレターで読んでくれている皆さん、本当にありがとうございます。
※次回は1/27(月)お届けする予定です
◉ ◉
※レターは月4本ほどの配信予定です。このレターは有料のサポートの方のご支援でお届けできています。わたしの「書く」励みにもなります。可能な方はご検討いただけますと嬉しいです。有料登録サポートメンバーの方には、限定公開の「このところ読んでた本日記」をお届けします(わたしには初めての日記体裁!)。
【主宰している場についてのお知らせ2つ】
●2月「ゲンナイ会」のこと
わたしが暮らしている神戸で毎月開催している「ゲンナイ会」という、読書会のような、自助グループのような会の受付のお知らせです。のんびりした会なので、ご興味ある方はどうぞ(1月は奈良の「ほんの入り口」さんで出張開催です。受付は終了しています。2月はあと1名受付可能かなという感じです)。
●「話を聞きます」受付開始のこと
一年半ほど前から、一対一でお話を聞く、インタビューセッションのような場を開いています。大学の授業がない時期だけ開催するので、1月下旬からの受付を再開しました。わたしは本当に話を聞くだけです。ちょっと不思議な場です。ご興味ある方はこちらをご覧ください。
すでに登録済みの方は こちら