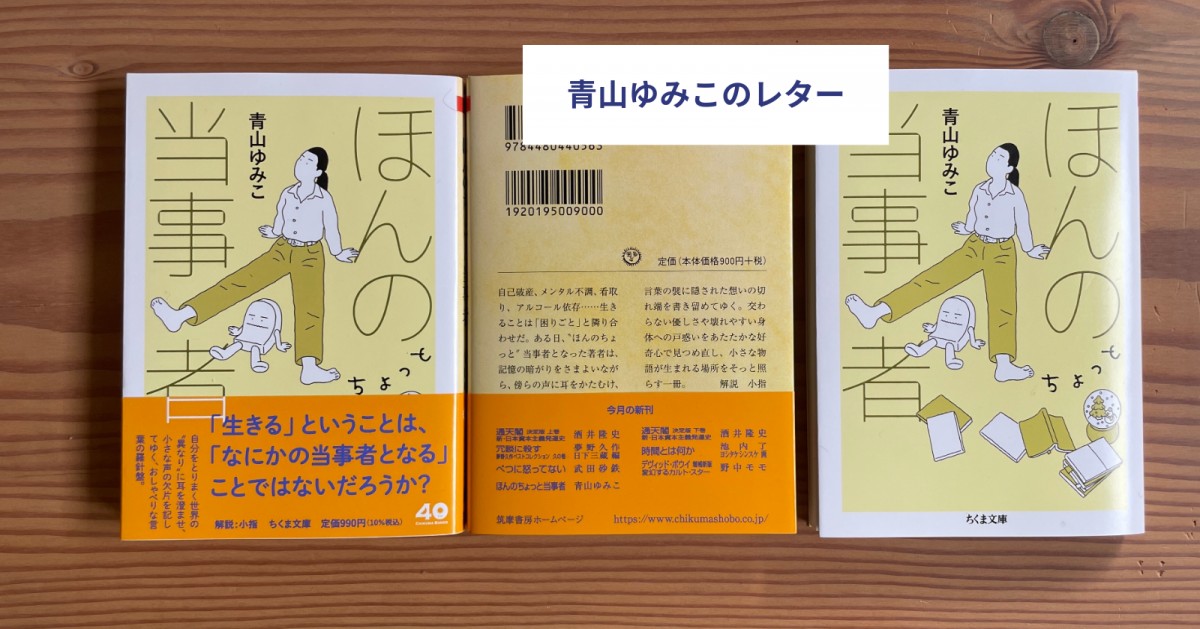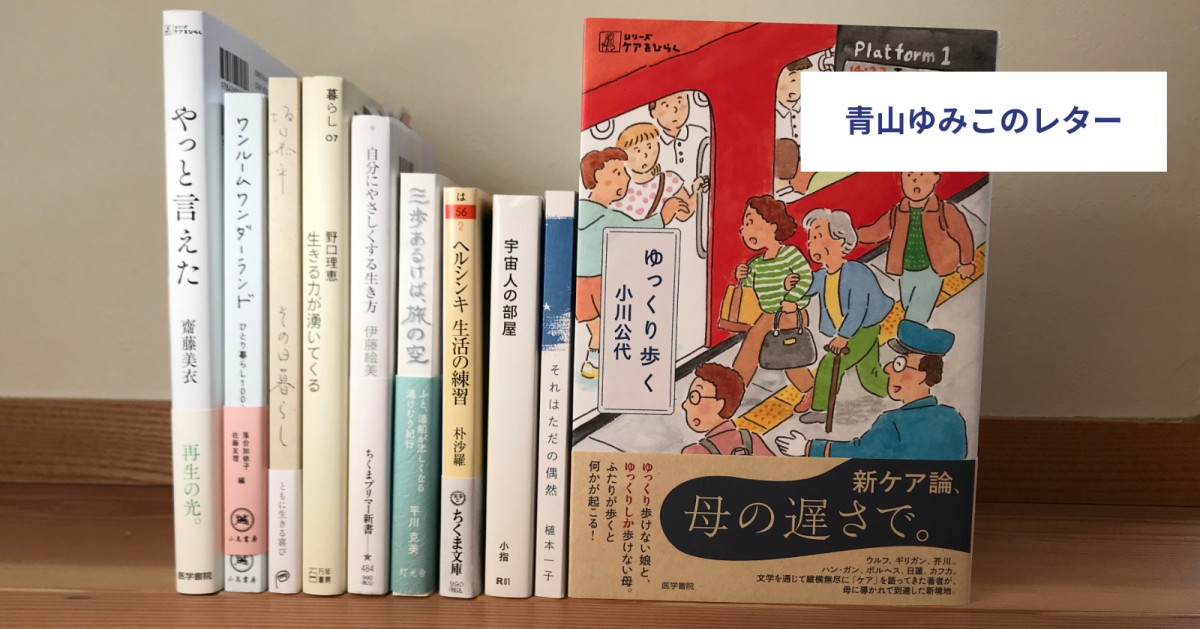30年間念入りに飲んできたお酒をやめて4年半。自分事としての依存症のこと(前編)
NHKラジオの「高橋源一郎の飛ぶ教室」、先週金曜(1/24)放送回の「ヒミツの本棚」で紹介されたのは、『酒をやめられない文学研究者とタバコをやめられない精神科医が本気で語り明かした依存症の話』(太田出版)。
この本はウェブ連載がもとになっていて、わたしも更新されるのを待ち構えていた一人だ。
なんせ毎回すごい熱量だったので、読みはじめると「クワァッッ」と全身の細胞がくっきり覚醒したような感覚になったり、時に読了する頃には「ふぉぅ……」と脱力したり。知的アッパー系、心象ダウナー系とでも例えたいようなダイレクトに「効く」連載だったことを思い出す。
お二人それぞれに文体も内容もまったく異なるが(そこが秀逸な往復書簡の妙でもある)、異様に中毒性が高かったというわけだ。と、肝心の内容についてひと言も触れず「すごい」「ヤバい」しか出てこない、三宅香帆さんの本でのサブタイトルどおりの状況になっている。
(参照:三宅香帆著『「好き」を言語化する技術 —推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』)
思わず「長いっ」と思わず突っ込んでもしまうけれど、実にわかりやすいタイトルでもあるこの一冊は、アルコール依存傾向がある文学研究者・横道誠さんと、ニコチン中毒を自認する精神科医・松本俊彦先生が、お互いに考え続けていることを広く、深く語り合っていくという往復書簡である(一文で説明できました)。

※サポートメンバーのご支援のおかげでレターを無料で公開できています。可能なかぎり毎週お届けしたいので、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
わたしはこの「やめられない往復書簡本」を、矢萩多聞さんが配信されている「本とこラジオ」の2024年大晦日スペシャルでも「今年の一冊」に選び、「好きです、最高です、超おもしろいです」と暑苦しく話したのだが、NHKラジオ「飛ぶ教室」を聞いてみると、高橋源一郎さんもかなり似たように前のめりで紹介されていたので、この本にそうした効用があるように思えた。
同時に、高橋源一郎さんの声に含まれる「熱さ」に、もう一つ理由があることを知った。「僕もギャンブル依存症なんです」という告白を聞いて。
なんと、当事者だったのか! そうか……。
『元気じゃないけど、悪くない』(ミシマ社)にも書いているが、アルコール依存症という診断はされていないが、わたしは限りなくグレーの当事者であると自覚している。2020年9月までの30年間、350日は泥酔していた自分。お酒をやめた今「当事者である」と書くか、「当事者だった」と書くか。時々迷うことがある。
依存症は「完治」がなく、「やめ続ける」ことが「回復」といわれている。それでいくとわたしは回復過程にあるだけで、過去形ではない現在進行形の「依存症の当事者」なのだと思う。
※NHKラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」(1/24回)は1/31(金)午後9:54まで「聞き逃し」で聞けます
●
急に少し話が飛ぶのだけれど、NHKラジオの「高橋源一郎の飛ぶ教室」を聞いたのは、番組の、というよりわたしが若い頃から高橋源一郎さんのファンだからなのです。そもそもTwitter(現X)を始めたのもこのことが理由なのです。
SNS戦国時代に入る前、まだネットの世界がのどかなブログ時代だった頃、わたしはココログにも自分のアカウントをもっていて、同じくココログ仲間の橋本麻里さんの「東雲堂日乗」と小田嶋隆さんの「偉愚庵亭憮録」の熱心な読者だった。
橋本麻里さんとはお互いにコメントを書きあったりしていて、お会いしたことはなかったが少し交流があった。
ココログか、他のブログかは忘れてしまったが、わたしは高橋源一郎さんのことを常々「好き」「ヤバい」と語彙力のなさを発揮して、世界の片隅から愛を叫んでいたこともあり、ある日、橋本さんが「そういえば、高橋がTwitterを始めましたよ」と教えてくださったのである。橋本さんが呼び捨てにするのは、彼女の父親だからだ。
Twitterってなに? とわからないまま、即アカウントをつくり、大至急、高橋源一郎さんをフォローしたのが2009年12月のこと。もちろん今でも「フォロー中」のトップは高橋源一郎さんのままだ。
つまり高橋源一郎さんがいたからわたしはTwitterを始めたというわけです。
さて、話はNHKラジオ「飛ぶ教室」の「やめられない往復書簡本」紹介に戻る。
さすがは依存症当事者、高橋源一郎さんが端的に本のポイントを紐解かれていた。
いくつかかいつまんで記しておきたい。
◉「習慣」と「依存症」に明確な線引きはない。僕らは境界線を動かしながら生きている。
◉なぜ人が「依存」するのか。あるのは「孤立」。必要なのは社会のなかでの「コミュニティ」。
◉ハームリダクションについて。
松本俊彦先生が科学的なデータや専門家としての知見をわかりやすく紐解いてくださっているので、ぜひ「やめられない往復書簡本」をお読みいただきたいが、聞き覚えがなくてピンとこないともったいないので、「ハームリダクション」だけ一部抜粋したい。
わたしはこの「ハームリダクション」の考え方がとても大好きなんです。希望を感じて。
===以下、引用===
薬物政策では、社会の偏見や差別意識が広がり、当事者を孤立させてしまいます。また、専門治療を受けたからといっても、長期の断薬を達成する人は一部です。
そこで、必要となるのがハームリダクションの考え方です。ハームリダクションとは、世の中には薬物使用を続ける当事者が必ず一定数いることを前提として、薬物使用を減らすのではなく、薬物による二次的な弊害を軽減することを目指します。具退例を挙げると、感染防止拡大のために清潔な注射器を無償配布し、安全な薬物が使用できる注射器を設置し、比較的害の少ない代替的薬物を投与するなどです。
それから、違法薬物使用・所持を非犯罪化(違法ではあるが罰は与えないこと)することで、当事者の治療アクセスを高めるとともに、収監による社会的孤立を回避させます。また、当事者が偏見・差別の対象とならないよう、たとえ薬物乱用防止の美名のもとであっても、当事者をゾンビやモンスターのような恥辱的表現で描写しないことを呼びかけます。
===引用終わり===
『酒をやめられない文学研究者とタバコをやめられない精神科医が本気で語り明かした依存症の話』(太田出版)「6_松本俊彦 周回遅れのアディクション治療」より
この本では横道誠さんの「語り」にもわたしは深く心を揺さぶられた。横道さんの正直さに泣ける。わたしも正直でありたい。担当編集者である藤澤千春さんのコメントもしみる(最高です)。
●
数年前から親しくさせてもらっているクロさんという女性がいる。わたしの少し先輩の世代だが、年下のわたしが同世代のお友達のように軽口を叩いてしまっちゃたりできるような、全く偉ぶったところのない方で、ポップでカジュアルなお洒落さんの見た目どおり、軽快で陽気でピュアなお人柄だ。
知り合ったのは5年近く前になる。ひょんなご縁からメールでやり取りするようになり、今になって思えば不思議なほど親密に話をした(オンラインではあるが)。
やり取りの頻度が高かったのが、わたしには愛猫との別れの時期とも重なって、同じく愛犬との思い出がある彼女からそっとあたたかい言葉をもらった。また、それからどんどん飲酒の量が増え、わたし自身や、家族のお酒の問題が大きくなったしんどかった頃、「よけいなこととはわかっているけれど」(文言は異なります)と遠慮がちなアプローチで、でも問題の核心にずばっと触れて、的確なアドバイスいただいたこともある。
彼女の家族が、かつて依存症の問題を抱えていたことは、知り合った当初からお聞きしていた。だからこそ、言いにくいことを言ってくれているのだ。親身に心配してくれているのだ。もちろん強く伝わってきて、その日のメールには泣きそうになった。
ただ、あまりに的確に急所を突かれたようにも感じて痛くもあった。むしろ当時は目を逸らしたい現実だった。だから逃げてしまった。
わたしがまだ問題に向き合う、向き合えるタイミングじゃなかったように振り返りもするが、「そんなタイミング」は自分からとらえることができない、と今はわかる。
「自分」というのは頑なで、手放すことが難しい。だから、クロさんのように、「余計なことを言って嫌われるかもしれないけど」という覚悟で、わざわざ声をかけてくれる人が目の前に現れた時こそが「タイミング」なのだ。
だけど、だけど、自分ではもうどうにもならないと心底納得するまで、人ってどうしようもなく動けない。わたしの場合はそうだった。
結局のところ、その後、わたしはお酒をやめた。だけれど、やめて「はい、すっきり!」とはならなくて、むしろ生活環境や自分自身の思考のクセなどを一つひとつ見直す必要が出て、かなり痛みの伴う治療とリハビリ期間を要したように感じている。
途中から人に助けてもらえるようになったが、いちばんしんどかった頃は孤立したのだと思う。孤立したことが、辛さを増幅したのだと。
あのときに「仲間」がいたらまた違っていたのかもしれない。クロさんが「仲間」がいるよって教えてくれていたところに頼れば、どうだったのかなとも。
彼女と再会、というかリアルに会うようになったのは、2年前の初夏。
不調のどん底でぐらぐらだった自分が、まだヨレヨレしつつもなんとか動けるようになった頃だった。コロナが少し静かになった時期だったこともあり、直接お会いしましょうとなった。
オンラインではかなり個人的に話をしていたが、リアルに会う楽しさ、距離の縮まりかたってやっぱりある。ずいぶんと長時間話しこんで、思い切り笑って、一緒に泣いた。人のことは言えないが、「なんてお喋りな人なんや!!」と驚いたりもした。
そんなクロさんは、お仕事とは別で、ARTS (Addiction Recovery Total
Support)という「薬物依存症の家族会」のメンバーとして活動している。わたしもARTSの家族会には何度か参加して、クロさんからいろんな人を紹介いただいて、皆さんに仲良くしてもらっている。
さらにはARTSと関わりの深い、「全国ギャンブル依存症問題を考える会」の家族会にも連れて行ってもらい、時々参加するようになった。それがきっかけで「ゲンナイ会」という読書会のような自助グループのような場も立ち上げてしまったほどだ。
わたしはアルコールの当事者で、薬物、ギャンブルと分野は異なれど、「依存症は病気で、家族だけで解決するのは難しいこと」「回復できるということを知ってほしい」「人が関わり続けることで、悪くないことが起きる」という思いは同じだ。
またわたし自身、依存症の当事者と家族のどちらとも共鳴する部分がある。「依存症」には一方向で片付かない多面的なところがあると改めて思う。
家族会をはじめ、こうした場に参加することでわたしは「仲間がいる」と励まされ、かなり救われている。そんなふうに誰かに助けてもらうと、人は同じことを誰かにできたらと願うものですよね。
自分のこと、家族のこと、お友達のこと……気になる方がいたら、どこかの会につながってみてほしいなと、思うのでした。
(つづく)
※後編はこちら(1/28 レターをお届けしました)
◉ ◉
レターの感想や読んで思い出したことなどあれば、SNSでぽそっと呟いてもらえたら嬉しいです。読んでもらってることが伝わってくると、ほんとしみじみ嬉しいものだから。メンバー登録いただいてメールレターで読んでくれている皆さん、本当にありがとうございます。
◉ ◉
※このレターは有料のサポートの方のご支援でお届けできています。わたしの「書く」励みにもなります。可能な方はご検討いただけますと幸いです。
【主宰している場についてのお知らせ】
●「ゲンナイ会」のこと
わたしが暮らしている神戸で毎月開催している「ゲンナイ会」という、読書会のような、自助グループのような会の受付のお知らせです。今後もこのレターで先行報告して、その後一般受付を開始、みたいなイメージにしています。のんびりした会なので、ご興味ある方はまたぜひ(2月はあとお一人受付可能かなという感じです)。
●「話を聞きます」受付開始のこと
一年半ほど前から、一対一でお話を聞く、インタビューセッションのような場を開いています。大学の授業がない時期だけ開催するので、1月下旬からの受付を再開しました。わたしは本当に話を聞くだけです。ちょっと不思議な場です。ご興味ある方はこちらをご覧ください。
すでに登録済みの方は こちら