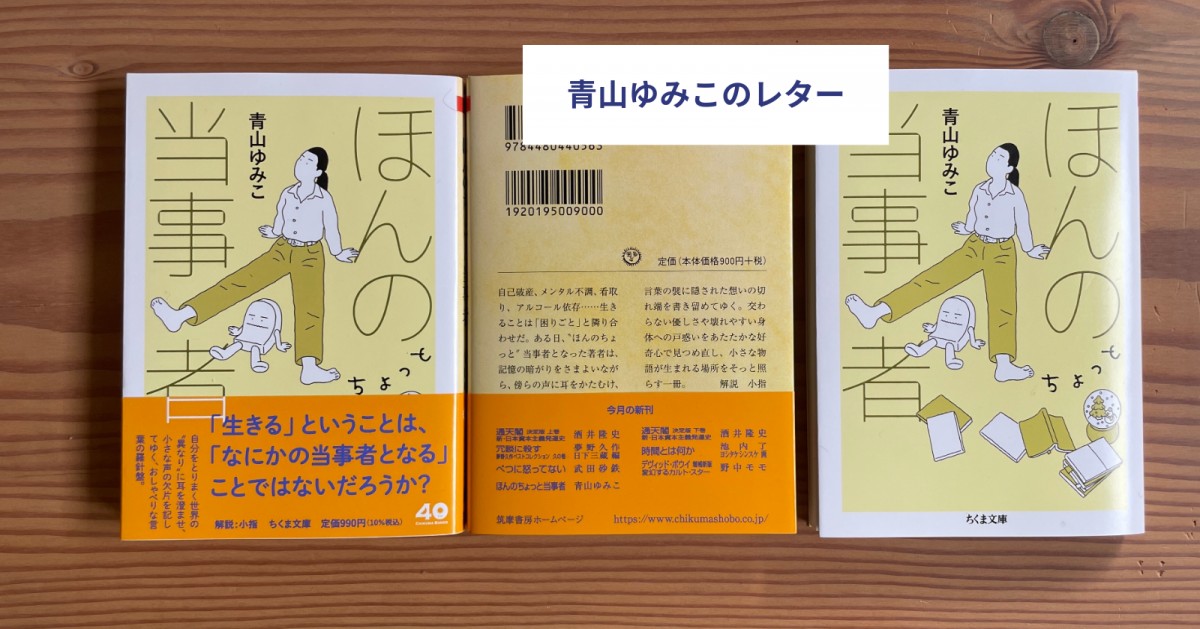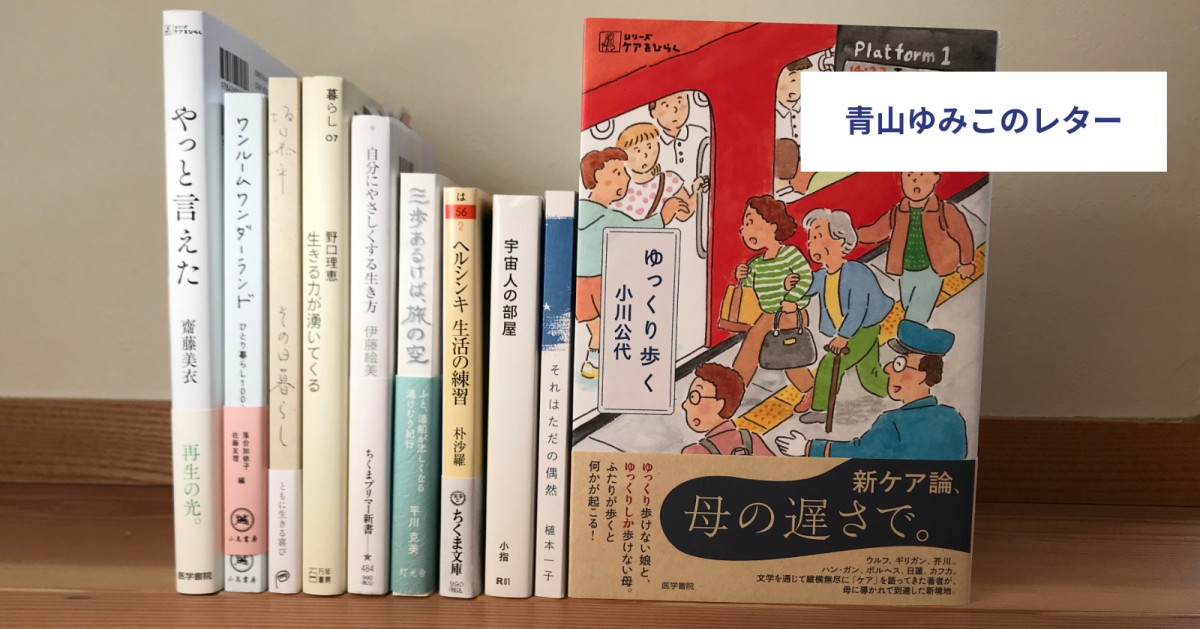アディクション界隈の素敵な面々(後編)。依存症専門メディアや精神科医の松本俊彦先生
先々週の日曜日(1/19)は、大阪の天満橋にあるドーンセンターでARTS主催の「薬物依存症セミナーin大阪」が開催され、わたしもオーディエンスとして参加した。
「薬物依存症」のセミナーと聞くと、「薬物」という語感からもしかすると、暗くて悲しい空気が漂っている会場をイメージした人がいるかもしれないが、むしろ逆で大きな会場は400名を超える人が客席を埋め、あたたかい活気に満ちていた。
当日は、「やめられない往復書簡本」の著者の一人である松本俊彦先生によるご講演から始まり、最近の薬物問題の主流である「市販薬・処方薬」の当事者家族のはなさんによる体験談、ARTS代表の田中紀子さんの「びしっ」と渇が入るようなトーク。
後半は、俳優やアナウンサーという「顔が商売」となる職業の人たちが(依存症でない、単なる薬物使用の方も含めて)、薬物問題でどういった影響を受け、どんなふうに皆さんがつながって、同時に回復していったのかを語り合うトークセッションという濃い内容だった。
深刻なテーマだし、現状の問題山積みぶりに重いため息も出たが、同時に、終始、希望がそこにはあった。このことを自分事として一緒に考えたいという、深くて強いつながりから生まれるなにかが会場全体から伝わってきて、胸が熱くなるような心持ちだった。
自分になにができるかといえば、こうして考えることをやめないってことだろう。自分事として考え続けること。依存症が、ごく普通の日常のなかにある、誰にでもなる可能性のある病気で、自分や家族とも関わりがあるかもしれないものだと思う自分の考えを、こうして話していくことをこれからも続けたい。
※ご登録(無料)いただくと、全文読めます。サポートメンバーのご支援のおかげでレターを無料で公開できています。可能なかぎり毎週お届けしたいので、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
クロさんの関わりとは別で、わたしは昨年から「Addiction
Report」という国内初の依存症専門オンラインメディアにライターとして参加するようになっていた。
遡って一昨年の夏、信頼する医療記者である岩永直子さんと、神戸でたまたま会う機会があり、その際に「来年の春頃に新しいメディアを始めるんです。依存症についての正しい情報を伝えるメディアを」と聞いた。
その日の話の流れで、わたし自身のアルコール依存傾向のあれこれをお伝えすると、「良かったらそのことを書いてもらえたら」みたいに軽くお誘いを受けていたのだった。
そんな流れがあって、昨夏から「Addiction Report」に記事を書かせてもらうようになったのだが、このAddiction Reportの母体は「全国ギャンブル依存症問題を考える会」という公益社団法人で、田中紀子さんが代表だ。そして田中紀子さんは、前述のようにARTSの代表でもある。
うまく伝わっているだろうか。ややこしい説明になってしまったが、つまりクロさんも田中紀子さんも、Addiction Report編集長の岩永直子さんもみんなつながっていたということです(ひと言で言えました)。
考えてみればわたしが初めて依存症治療専門医として松本俊彦先生の名前を知ったのは、岩永直子さんが医療記者として取材された記事だった。
依存症への情報が錯綜するなかで、偏見や誤解をなくし、わたしたちが暮らす社会を一緒によくするために「知ってほしい、自分も知りたい」ということが伝わってくる丁寧な取材と真摯な姿勢が届いてきた記事だったから、深く印象に残ったのだと思う。
実際にお会いして話をした岩永さんは、やはり裏表のない物言いと真っ直ぐな性格で、仕事をご一緒するようになった今、記者という仕事に対する強い信念をいつも感じる。
ギャンブル依存症の当事者であり、当事者の家族であり、回復者であり支援者である田中紀子さんについてはまた改めて書きたいが、これまでたくさんのキャラの濃い人と出会ってきたわたしだけれど、インパクトの強さでいくと破格のお一人だ。
頭の回転も行動も早く、なにより困っている人を見過ごせない超級のお節介体質。時にそばにいると火傷しそうに熱く、でもその炎でどれだけの人が救われてきただろう。泣きそうになる。
家族会などで、間接的にお世話になりましたという生温い話ではなく、リコさんにぐいっと腕を掴まれるように「リアルに助けられました!」という人によく会い、声を聞く。その数の多さに圧倒される。ほんとに一人でそんなにたくさんの人を……。分身の術でも使えるのだろうか。
というわけで、前編で触れたように、もともとはお喋り友達だったクロさんとは依存症を考える流れでもつながって、人のご縁って本当に不思議だなあと感じている今日この頃である。
さて、この話も聞いてほしい(それで長くなってしまいました)。
今までオンラインのイベントがあると聞けば欠かさずチェックし「申込み」連打し、ウィットに知見に満ちたお話にうっとり聞き入って、遠くの星を眺めるように目をハートにしてきた松本俊彦先生だが、なんと初めてお会いすることができてしまったのです(自分的には大事件)。先々週のARTS主催「薬物依存症セミナーin大阪」で。
クロさんがお忙しい合間を縫って楽屋に誘ってくれて、松本俊彦先生(いちいちフルネームになってしまうのはファンだからです。村上春樹的な)に紹介してくれたのは前半と後半の幕間のこと。でもわたしは尊い存在が目の前にいることにあまりに緊張して、名刺を渡して挨拶するだけでもう必死。「余計なお手間は取らせません」とばかりに過剰に事務的にすらなっていたかもしれない。
同じ部屋にリコさん(田中紀子さん)もおられて、いつものように朗らかな大きな声で「あ、青山さ〜ん、こんにちはっ」とお声がけくださったのに、動揺しているわたしは「あ!どうも(ぺこり)」くらいしか返答できなかったほど(リコさんもお忙しそうだったし)。心のなかでは「リコさん〜〜〜」ときゃっきゃなっていたのに。
その控え室には橋爪遼さんもおられたので、映画『アディクトを待ちながら』ではあの表情にものすごく感動しましたと、なんとかお伝えさせていただいた。
ああ、アナウンサーの塚本堅一さんもおられる。今日の進行もさすがですとお伝えしたい……ということは1ミリもできず、もうだめだと逃げるように楽屋の控え室を去って、フロアに戻るとどっと汗が出てペットボトル500ミリを一気飲みした。
会の終了後、クロさんがまた駆け寄ってきてくれて、サイン会真っただ中の高知東生さんにもわざわざご紹介くださったけれど、もう自分がいっぱいいっぱいすぎて『生き直す』(青志社)を読んで感銘を受けました!『アディクトを待ちながら』の即興には震えました!!ということを0.01ミリも伝えられなかった。
無念だったので、ここで書かせていただきます。
クロさん、ありがとうございました。
リコさんがつくってきた「場」、そこで生まれた「つながり」。それをどんどん広げていこうとする情熱にも尊敬の気持ちしかありません。
家族会の皆さんとのつながりが、わたし自身のアルコール依存の回復過程をこうして今も支えてくれているのだと感じています。
皆さんへの御礼の手紙になってしまいました。
※サポートメンバーのご支援のおかげでレターを無料で公開できています。可能なかぎり毎週お届けしたいので、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
最後に(まだあるのか……ごめんなさい)、2年ほど前、松本俊彦先生のご著書について書いた文章を貼ります。いろんなものが炸裂してお恥ずかしいのですが。
◉◉
好きです松本俊彦先生(というラブレター)。
『誰がために医師はいる』(みすず書房)
2022年12月08日

今年もたくさん「読めてよかった〜」となった本が多くて、わたしは「本と出会う運」がどうしてこんなにあるのだろうと、ただただありがたい。12月に入ったし、この一年で出会った本を少しずつメモしていこうと思います(発行年月は関係なく、自分が2022年に出会ったという意味です)。
読後の感触が読む前の想像と今年最も異なった一冊が、松本俊彦著『誰がために医師はいる』(みすず書房)。
もうめちゃくちゃ面白い。
みすず書房の「凜とし過ぎ」にさえ感じる佇まい(悪口ではありません)、純文学への素養が踏み絵のようにも感じるタイトル、けわしい活字山を登頂してきた人のみに踏むことを許される積雪のような静謐なデザイン&書体、「偏見、分断、刑罰」と偏差値も意識もごりごりに激高っぽい帯文……。
わたしのようなぼさっとした者に読める本じゃないのでは……と、実は書店で何度も棚の前で悩んでは、あまりに尊いオーラに手が出せず、やっぱり立ち去る、みたいなことを繰り返したという経緯もある。
「けして気軽に手に取らせない!」という決意に満ち満ちたみすず書房らしい本の存在感。思惑どおりに撤退していたわたしだった。
大きく背中を押してくれたのは、元阪大医学部教授・仲野徹先生と松本俊彦先生の対談をオンラインで拝見して、話をしたり聞いたりする様子を目にするや、遠慮がちではにかむような姿に「松本先生、素敵」「俊彦ラブ」と胸がきゅんとしたことがひとつ。動く松本先生のチャーミングさたるや……(きゃああ)。
加えて、友人が関係していることもあり、手に取ったムック『安克昌の臨床作法』(日本評論社)に寄稿されていた文章が、めちゃくちゃ面白く(興味深く)、素人にも親切で、こんな文章ならもっと読みたい! となったからだったのでした。
嗜癖障害(アディクション)の臨床に携わってきた、いわば専門医の自伝エッセイなんだけど、門外漢のわたしがあまりに話が面白くて声を上げて何度も大笑いしてしまいつつ、現場で起きていること、松本先生の心境の吐露に、胸が熱くなったり締めつけられたり。
ぐいぐい引っ張られて、「面白い」という感覚でただただ夢中で読み終わる頃には、アディクションのさまざまな深刻で生々しい現実や悲喜こもごも、知識、社会の課題を山のように受けとっていた。
ずば抜けた文才が炸裂している。いや、「ずば抜けた文才」なんて陳腐な言い方が恥ずかしいほど、真摯でユーモアに満ちている。 ああ、ほんとにすばらしい一冊だ。
読後思い出したのが鈴木智彦さんの『ヤクザときどきピアノ』(CCCメディアハウス)でした。どちらの本も内容はかなり専門性が高い。『ヤクザときどきピアノ』は、「ヤクザ取材」という、いわばルポルタージュでも取材の難易度が高い現場についてもそうだし、「ピアノ」という楽器、そして「楽器演奏の習得過程」について、多面的かつ、それぞれ濃密な深度で迫る一冊だ。なのに、するする読んでしまう。読めてしまう、という気にさせる。
『誰がために医師はいる』は、「アディクション」という、言葉で説明するのがむずかしい現象についての研究レポートでもあるんだけど、まるで素人の読み手のわたしが、驚くほど読めてしまう。読むというより、読めてしまう。すごい。